“伝統”数秘学批判
──「公然と隠された数」と周回する数的祖型図像 [10]
“3”の時代〜「元型的火曜日」(下)
Saturday, April 15th, 2006
■「三日目」を表す「三日月の象徴」の登場
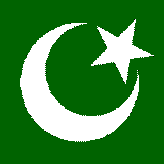
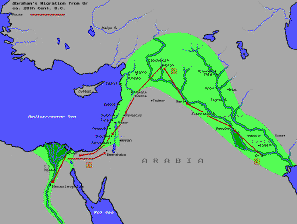
巨大スケールの「分断: schism」によって衰退の色を濃くしていくローマ帝国を、決定的に弱体化させ滅ぼした幾つかの要因のうち、帝国領土への物理的浸食という極めて直接的な関与をしたのが、後の近代国家としてのドイツを造るゲルマン民族のはたらきであるが、加えて何よりも無視できないのが勢力を拡大するイスラム帝国である。そしてここでわれわれはイスラム教が「三日月の象徴」を保持していることを思い出さなければならない。
「三日月の徴」がイスラム教のシンボルであることについては、当然のことながら「顕教的に正統」とされる伝説的エピソードが伴われている。イスラム教という宗教が紛れもなく「月」によって象徴されるいくつかの性質や約束事を持っていることは至る所でその記述を見出すことができる。(エリアーデ『シンボルと宗教』参照) だがそれが視角化されるとき、「半月」や「満月」ではなく「三日月」でなければならなかったことには、単に「月」としての認知しやすさのみならず、複層的な意味合いをわれわれは見出すことができる。
預言者マホメットに最初の神託が訪れたのが「三日月の晩」であったという有名な説話が「三日月」の根拠のひとつである。だが、われわれが気を付けなければならないのは、そうした説話の持っている二重の意味性である。これは実際にその奇跡が起きた当夜が、旧暦(陰暦・月齢)の第3日であったという「歴史的事実」を伝達することだけに目的があるのではなく(それ自体には象徴的意味合いをおいてなんらのsignificanceもない)、むしろもっと大きなわれわれの「歴史時代」において、マホメットの登場(イスラム教の勃興)が(象徴的な)“第三日”であったということをも伝達するのである。
ユダヤ=キリスト教の秘教の地下水脈を辿ることで祖型的図像群中の「数性」の実在を論じるのが目的であるのでここでは深入りしないが、イスラム教の存在と、約束されたかに見える将来における一定の役割は、こうした秘教的な壮大な文脈の中に完全に組み込まれていることであるとだけ、ここでは記しておく。[将来『集団的な浄化儀礼と<三日月>の伝えるもの』で若干の詳述をする予定]
■ 前近代国家の「数性3」神聖ローマ帝国の子供たち(17世紀 中欧/東欧)
「数性3」の時代の中間期において中心を成すのが、その後近代国家になっていく、ドイツそして東欧諸国を含む(三色旗を持った)ヨーロッパの中でも相当に広範な領土を含む地域である。それはまさに“第3のローマ”とも言うべき神聖ローマ帝国のことであり、そのこの時代における役割を無視するわけにはいかない。この「最後のローマ」は長い「三の時代」の最終局面を含む。すなわち962年にオットー1世(大帝)がローマ教皇ヨハネス12世によって、古代ローマ帝国の継承者として皇帝に戴冠したときに始まり、「三十年戦争」の後、1648年のウェストファリア条約によって封建領主の独立主権が認められ、帝国は300の領主国家に分裂するまで続く。ほぼ700年間続くこの世俗権こそが、後の近代国家の数々を産み出す土壌となる「帝国」なのである。
そして神聖ローマ帝国は、ドイツ王国(フランク王国)・イタリア王国・ブルグント王国という言わば「3つの連合王国」を包含することにわれわれは注意を向けなければならない。このように「包含される国(王国)の数」というのが、ある数性を同時に象徴するというのは、実はローマが東西二つに分断された時点に始まり、この「3つの連合王国」に引き継がれ、後に華開く欧州中心的世界における象徴的国家構築の「祖型」となっていくのである。
この時代の最終局面において、ウェストファリア条約によって解体された神聖ローマ帝国は、ヴォルテールによって「神聖ではないし、ローマ的でもない。それどころか帝国ですらない: The Holy Roman Empire is neither Holy, nor Roman, nor an Empire. / Ce corps qui s’appelait et qui s’appelle encore le saint empire romain n’?tait en aucune mani?re ni saint, ni romain, ni empire.」とさえ言われ揶揄された。この「最後のローマ帝国」の細分化こそ、現代に連なる「数性3」を伝統的に保持したまま、近代国家生成の種を、欧州全土に蒔くのである。
■ 近代国家時代の「三色旗」支配の時代
|
|
イタリア |
|
|
ベルギー |
|
|
オランダ |
|
|
ハンガリー |
|
|
ドイツ |
|
|
ブルガリア |
近代的国家が、その国の象徴的基盤として「数性3」を持っていることは、今日ではそれらの<国旗>を通じて最も雄弁に表現される。現在欧州で数種類の色の組み合わせがあるものの、三色旗を持っている国々は主に“3”に象徴される各国の王に対する法王による「戴冠権」(指名権/許諾権)を独占する権威的組織としてのローマ・カトリック(すなわちローマ帝国の宗教)による支配を受けた国(後にプロテスタント側に鞍替えするものも含めて)、もしくは神聖ローマ帝国の一部を成していた国々である。このことは、「数性3、4、5(そして6)」と続く「数の進行:曜日の進行」の文脈を未だ明瞭に語れぬ現時点ではにわかには諒解しにくいことであろう。
「黒・赤・黄」の三色旗は、ドイツ、ベルギー、「緑・白・赤」がイタリア、ハンガリー、「緑−白−橙」がアイルランド、インド、また旧チェチェン共和国)となっている。特殊なところでは「青−黄−赤」の三原色*を用いたルーマニアとアンドラがある。「青・白・赤」の三色を基調とする国家にフランス、オランダ、ルクセンブルグ、(それに旧チェコスロヴァキア)がある。
われわれは一般的に英・米の国旗を「三色旗」とは呼ばない。だが中でも「青−白−赤: Blue, White and Red / Red, White and Blue」の三色を基調とするこれら仏・英・米の三国は、その共有する色が示すように、今日、まさに「三位一体」である。そして、世界中に植民地を持つなど世界に対する支配的覇権を揮う経歴を持つ国々である(ここでは取り上げなかったが、同様の三色旗を持つオランダ**もそうした国家の例に漏れない)。いずれも時代の各過渡期において競い合い、また牽制し合ってきた関係だが、とりわけ仏・英・米の3国の「一体関係」は20世紀初頭から第一次、第二次両世界大戦を通じて濃厚になっていく。後述するが、特にイスラエル建国を始めとする中東政策を巡って、この3国の間にはある種の「申し合わせ」が存在するかのように一層一体感を強めていくという過程を目撃しており、その事実をわれわれは既に無視するわけにはいかない。また後にそれを思い出すことになるであろう。
* ルーマニアはローマ人の国、アンドラはフランスとスペインに挟まれたピレネーの小国。現在はフランスの大統領(世俗権)とスペインの司教(聖職権)によって統治される二頭制の国家。この三原色は、「ヨハネの黙示録」において幻視された「2億の騎兵隊」の三色の胸当ての色に一致することに注目すべきである。
** 現在、オランダの三色旗は上から「赤・白・青」の三色になっているが、一番上の「赤」は以前は「オレンジ」であったことが知られている。オレンジ公ウイリアム(ウィリアム3世)のシンボルにちなんだものと言われているが、オレンジ色のトーンを維持するのが技術的に困難で、後に赤に「変更」されたという説明がある。だが、それよりもフランス革命による影響が免れなかったオランダが「自由・平等・博愛」の理念とそのシンボルである三色を相続したと考えるのが自然である。オランダはフランス革命後、「本国の消滅」という期間があったが、このオランダの極東における地位の激変期にも、長崎の出島の商館長ドゥーフはオランダの三色旗を掲げ続け、再興されたオランダに帰国後国王から勲章を受けている。オランダ国旗は1630年以降、「オレンジ・白・青」から現在の「赤・白・青」に変わったのであるから、出島にはおそらく現在我々が知る“Red White & Blue”のTrois Coleursがすでに見られたということが想像できるのである。
■ 「数性3」の権化としてのフランス


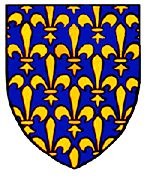
図版引用先:
右上:Armes de la Maison des Bourbons de France (avec les Fleurs de Lys : symbole de la royaut? de Charlemagne) @ Histoire et Documents
上:Philip II the King of France @ Wikipedia
バルカン半島から北部/東部にかけてのヨーロッパで影響を持っていた神聖ローマ帝国と平行するかたちで長期にわたり厳然と存在し続け、ローマ・カトリックの権力を具現化するための世俗王権としてその「文化」的影響力を揮い続けたのがフランスである。そしてあらゆる「数性3」の表徴を主張し続けたのがフランスである。
フランスにおいて起きるその時代を画する大きな事件のいくつかは、その国の役割を象徴するものである。時間はやや前の時代に遡るが、そのうちのひとつは「アルビジョア十字軍」と呼ばれる大規模な軍事行動を含む「異端」カタリ派(アルビジョア派)に対する徹底的な宗教弾圧である。これは12世紀末から13世紀初頭に掛けて行なわれたもので、この地におけるローマ・カトリックの勢力を確固たらしめ「フランス」(王家)の領土拡大をもたらすために、多大な意味を持つと言えるであろう。そしてもう一方はフランスの「独立国家」としての最大の危機と、その際に体験された「受難」として記憶されるものである。それはイギリスとの間で闘われた「百年戦争 (1337-1453) 」での時代であると言っても過言ではないだろう。
● カタリ派弾圧の意味すること
カタリ派の弾圧は、いわば今日のフランス国土の極めて大きな範囲を巻き込んだ一種の内戦とも呼ぶべき時代的エポックである。キリスト教の成立期に既に記録されているカタリ派の存在は、この時期の政治闘争に敗れたため実質的にカトリック側から一方的に「異端」というレッテルを貼られているが、それはひとつの大きな宗教運動の潮流であった。カタリ派はグノーシス主義の一種であり、グノーシス主義とは「ゾロアスター教、古代哲学、およびキリスト教の三大潮流の合流点に位置する大きな思想運動であった*」。
そしてこの思想とは単純化を恐れずに記せば、「善と悪の二元論」というものであったとさえ考えられるであろう。ゾロアスター教を単なる二神論であったと断じるのは危険であるが、カタリ派の思想はキリスト教成立以前にすでに起きていたある種の二元論的世界観を反映し、そして何よりも現世を「悪の究極の原因たる物質世界*」と観る。ここには「悪」の存在が神の業から切り離されて厳然と実在するという世界観がある。そしてその現世世界は滅ぼされなければならず、ゆくゆくは神(善)の支配が訪れるであろう、という考えである。
こうしたグノーシス主義は西暦216年にバビロニアで生まれ(だが血統的にはペルシャ人)マニ(マネス)によって始められた新宗教「マニ教」に受け継がれる。そしてその宗教は彼の生前期にそれなりの信者を集める。後にキリスト教に「改宗」する聖アウグスティヌスも最初はマニ教徒であったことを考えれば、当時相当のポピュラリティを持つ宗教であり哲学思想であったと考えることができる。あるいはマニ教が後のキリスト教という一大宗教に合流する一群の学者や信者をある程度まとめあげる機能を果たしたということもできるかもしれない。マニ教自体は、マニの生きていた時代に積極的に支持をしたパトロンの死去に伴い急速にその影響力を失うのであるが、その後も800年以上に渡って様々に「異端」と決めつけられるキリスト教宗派として名称を変えながら、地下水脈的なグノーシスの思想的潮流として生き延びた。
このマニの教義がグノーシス説のひとつであることからも想像できようが、精神界と物質界の併存、すなわち「神(精神)と物質(肉体)の絶対的な二元併存*」を最初の前提とする。つまり肉体的存在(悪)が神(の計画)によって産み出されたものではなく、「悪」ないし「物質」として自力で存在することを認める理論なのである。つまりこのふたつの対立する本質的存在の上に「上位の神*」が想定されないところにこの思想的潮流の特徴がある。ローマの「本流」からすれば、これがカタリ派が「二神論」的と決めつけ、徹底批判する口実となったわけである。
* 参考:フェルナン・ニーム著『異端カタリ派』(クセジュ文庫)より
だが、ローマ・カトリックのその後に開花する教義とは、マニ教以上に「いびつ」であるとしか思えない「三を以て一と捉える」“三元論”的な理論であったのは、われわれのすでに知るところである。ただし、天上にいる神(父)と地上的存在である我が「人の子」と、それらふたつを結びつける「媒介」としての「精霊」の存在を積極的に認めることで、「それはひとつの神なのだ:唯一神なのだ」という理屈へと発展・進化する。

図版引用先:Philip II the King of France @ Wikipedia
手と冠に黄菖蒲の象徴が描かれる「フィリップ・オギュスト」とも呼ばれるカペー王朝の王。ドイツ皇帝と連合したイギリスから北フランスを奪還した(1214年)英雄と評価される。カタリ派に対する徹底弾圧を強行したインノケンティウス三世の命により組織された「アルビジョア十字軍」という、仏国内における悪名高き異端討伐軍参加を命じられる。実際は殆どこの異端征伐問題に立ち入らずに王領拡大という旨味が転がり込む。
すなわち、12世紀末から13世紀に掛けて「フルール・デ・リ」の象徴を抱くフランス王家によって行なわれた「ネオ・マニ教徒」とも呼ばれるべきカタリ派に対する徹底的な宗教弾圧は、「数性3」の象徴を持つ人々による、前時代の生き残りの「数性2」の保持者たちの殲滅の意味があったと捉えることができるのである。
● フランスと「百年戦争」
14世紀半ば前(1337)に開始され、まるまる1世紀以上に渡って繰り広げられた百年戦争こそ、現在のフランスの王位継承権を主張した「3人」の継承候補者の登場によって始められる(その内のひとりが欧州大陸への領土的野心を持っていたイギリス国王エドワード三世であった)。そして、その百年以上に渡って続けられたフランスの英国との闘争は、言わば中世におけるフランスの民族と国土が、その後の近代国家フランスへと連なる歴史動向の中において、ひとつの自立的意識を決定的に根付かせるだけの強さを持った文字通り「受難」の過程であった。
それは第一義的には「シャルル四世の突然死」(早すぎた死)に始まる王位継承問題を発端とする英仏間で繰り広げられた実力行使を含む長期的な対立であり、権勢を伸ばし始めた「次の帝国」たる英国を退けその影響からの脱却を進めるものとしての意義もある。そしてそれはジャンヌ・ダルクの登場とその「犠牲的受難」ないし「人身供儀」によって劇的に幕を閉じる歴史的エポックとなる。
フランスにおいて女性が殉教者として国を代表する聖人となったという事実は、フランスの持つ国民性とも集合的無意識の反映とも言い得、きわめて象徴的である。これは福音書における代表的登場人物であるキリストと使徒のあいだの関係から読み解ける各登場人物の役割が、ヨーロッパの近代国家のいくつかに当てはめられるということ、そしてそうした呼応性の中で確固とした(しかも下意識的な)役割を宿命的に担っている欧州の国々を考えたとき、フランスにおける代表的偉人が他ならぬ女性であったというのは、納得できることなのである。それは女使徒としての「マグダラのマリア」とフランスの間に暗示される関係*についてであるとここでは一こと言及しておくことに留める。
* ここでは詳述できないが、寺院の名前でも知られるノートルダム: Notre Dame(我らが貴婦人)は、通常「聖母マリア」を意味する代名詞として信じられている。しかしエソテリズムの世界においては二人のマリア(聖母マリアとマグダラのマリア)の間には、「マリア」というコードで提示されるある種の「意図された混同」があり、ひとつの女性的原理によって表される実体の「ふたつの側面」を表すものであると考えられるだけの一定の理由がある。そしていかなる固有の名称で呼ばれようと、「キリスト教会」という存在自体が、「安息日に客を取りサービスする」ことを商売(なりわい)としている点で、現福音書におけるマグダラのマリアのエピソードの指し示すものとの呼応性があるのである。
いずれにせよ、「フランス」という国が女性聖人に与えられたコード名によってその役割の位置付けがされている以上、その時代(“3”の時代)を画する殉教者は女性でならなければならなかった。


図版引用先:Joan of Arc @ Wikipedia
ジャンヌ・ダルクの登場とその死 (1430年)は、大きく敗退し荒廃したフランス国土の英国からの防衛と独立の契機となった。その結果、フランス独立の“女傑”としてジャンヌ・ダルクは認識されている。そして彼女が護ったのは既に言及した「フルール・デ・リ」によって象徴されるフランス王家なのであった。そして「早すぎた英帝国の登場と退出」がわれわれの記憶となっているのである。
フランスと“3”の関連は、三位一体を表す黄菖蒲(アヤメの一種)の紋章 (fleurs des lys)がフランス王家の紋章となっていることや、近代国家としてのフランスが三色旗を抱いているということ以外に、「ボルドーの巡礼者: the Pilgrim of Bordeaux」が、西暦333年に新約の有名な舞台のひとつ、ゲッセマネの場所と信じられている「オリブ山の麓」の聖地を訪れたという古い記録からも伺える*。(Catholic Encyclopedia)
* それ以外では国際電話の国番号がフランスは「33」になっていることを無視することはできない。
●“3”の時代と三位一体の本質(まとめ)
ローマ・カソリックこそが「父と子と聖霊」が一体であるという三位一体説“Doctrine of Holy Trinity”を唱え流布した張本人であるのは、観てきた通りであるが、この説は三つの異なる存在が「同一」であるという「数性」に絡む謎(そして最大の謎)をヨーロッパの記憶に遺すことが目的であったかのようでさえある。このアヤメ(カキツバタ)の紋章を始めとする<兆し>は、その三つの花弁が一つに束ねられるその図像を以て、その「一体性」を象徴しているのであるが、それの真に提示しているものは、紛れもない「数性3」である。「三位一体」説こそ「父と子と聖霊」が同一である、という抽象的で理解困難な原理の受け入れを迫るものではなく、それは単に世界に向けて「数性3」を歴史に示すために登場したに他ならないかに見えてくる。しかも、教会の「三位一体」説を巡り議論が白熱し、それが歴史的にさらなる論議を巻き起こす程に、そしてそれが暴力的なまでの「異端審問」を通しての思想弾圧が高まる程、恐怖を人心に引き起こすひとつのサイン(徴)となった。そしてその運動が、その内容の本質とは関わりなく、意味のあるひとつの範型的イメージとして人類に記憶されるという仕組みになっていたのだ。
時に常にひとつの時代が終わり、次の時代へ移行する際、大きな争乱が起こる。“3”の時代から“4”の時代への移行でもそれは例外ではなかった。歴史の舞台はヨーロッパ本土から、ドーヴァー海峡を越えて、ヨーロッパ「辺境の土地」であるブリテン島に移る。歴史的にわれわれが諒解するところによれば、「ヘンリー8世の離婚の正当化」のという世俗的試みが契機になり、ローマ・カソリックの呪縛から逃れるべく英国王朝は、1534年、ついにイギリス国教会の独立を獲得する。そして今度は、ある濃厚な数性を抱いた<徴>を背負った人々が、クリスチャンクロスならぬ「ある徴」を旗めかせながら、通商活動と称して世界を飛び回る。彼らこそが「翼を付けたメッセンジャー」として、本格的活動に入るのである。





