壷の底に見出されるもの
(あるいは「壷を焼く」という儀礼に関わる)
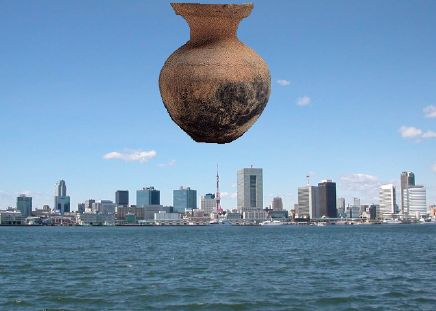
轆轤(ろくろ)を使って作ったと思われる壷なども含め、もっとも簡素な素焼きの土器の多くが、一見、地面に自立できないような丸まった底になっているのは、おそらく立てるための三脚状の道具が別にあったか、地面の窪みにそれを直接嵌め込むか、その辺りの機能上の理由のためにそうなっていると想像されるが、平らな場所に自立させておくことができない意匠の壷が、これほどの数で古今東西のさまざまな民族の古代遺跡から発見されるという事実には、別の隠れた意味の存在を考慮してみる必要があるのではないかと考えさせるものがある。
一年草の植物のライフサイクルのパターンは、発芽があり、伸張と成熟があり、花を咲かせる時期があり、結実があり、最終的には枯死がある。そして枯死には播種が伴われることがある。この、季節の巡りに併せて一見終わったかに見えるひとつの生命史は、来る年の迎春における「発芽」という劇的な復活のエポックを経て、再び誕生から枯死へのサイクル(周回)の途に就く。これは通常、植物の典型的特性として理解されている。それはまた、まったく正当な理由により、錬金術の象徴体系に用いられる比喩としても登場する。
一方、動物のライフサイクルは、誕生と成長があり、成熟した個体が生殖によって子孫を残し、その役割を次世代にバトンタッチして終えるというパターンをとるので、普通そこには生命活動の断絶は存在しない。冬眠行動をとらない限り、そこには仮死状態を連想させるようなライフサイクルの休止局面がないのである。仮に冬眠したとしても、これは次世代への生命継続の連携とは無関係である。ヒトの個人の人生について言えば、このことは他の動物と同様で例外ではない。植物のライフサイクルと動物のライフサイクルには対照的な相違が認められるのである。
だが重要なのは、集合体としての人間――人類の歴史(文明)――が、まさに植物のライフサイクルを思わせる範型を持っているという事実である。
人間が「文明の極」への旅の第一歩を踏み出す(それは終局の直後から始まる)とき、人間の手によって造り出されるあらゆる道具が、記憶にも新しい「人類の上に起こったある悲劇的できごとと同様のこと」をふたたび引き起こす、発端の萌芽があるということに気付かないほど彼らが愚かであったとは考えにくい*ことである。彼らは、われわれよりも「そのできごと」に遥かに近い、いわば「戦後」を生きていたのである。その畏怖すべきできごとの原因が、人間の道具に依存する、いわば「モダニズム」や「改革性」の中にこそ潜んでいることは、彼らなりの方法で伝承されていた筈である。
* 唯一神への信仰を強要する普遍宗教の類が強調する「偶像崇拝の禁止」とは、キリスト教のイコンのような宗教的な崇拝対象物に限るものではなく、実は「あらゆる人為的創作物への崇拝の禁止」であったと考えられる論拠がある。人間が人間の手によって作り出すものを絶対のものとして崇拝することは、人間が人間の潜在能力を過信することを意味し、人間によって解決できないものはないとする人間の自己愛と自己過信へとつながっていくのである。その自己過信が、人間自身によって解決することのできない問題を人間自体が作り出すことになり、それが人間自身を一旦完膚なきまでに滅ぼすのである。
さまざまな場所で採られてきた伝承のための儀礼的道具(記憶術)が、例えば貝殻であり、あるいは紐で束ねられた収穫物であり、または植物のタネや葉なのである。大規模施設としては、前方後円墳のように「墳墓」として信じられているような儀礼場も含まれる。そしてそれぞれの持っている形の中に、古代の人々が維持した記憶を連想させる記号を見出すのだ。むろん、それを連想させる理由は、「メメントモリ(死を想起せよ)」という言葉で以て、自戒の念をいくどでも想起させる、古くからの習慣と根を同じくするものであることはいまさら言うまでもない。
その記号は、宝珠のような、キツく絞られ細くなった「軸」ないし「支柱」を下部に持ち、その一定の長さの軸(支柱)が、あるものの上昇運動の「軌跡」に一致し、それが上空で炸裂するというような、花火や薬玉と言った祝祭的な儀式にも通ずるような、ある種の運動や化学作用の様態、そしてそうした祝祭を連想させるある種の物質の爆発的な膨張を表す「量的」な象徴物となる。これはできごと自体(コト)を表す。
そして、この「キツく絞られ細くなった軸」を持つ形状は、その輪郭が鍵穴のような形状として表されることがあり、またその輪郭は羽根を持ったシャトルコックの様な形状そのものである場合がある。これは「できごと」自体ではなく、「できごと」を引き起こすモノを表す。
これら結果としての「できごと自体」とできごとを引き起こす「原因物」の両方を表すことのできる、きわめてまれなひとつの道具とそれらの形状の持つの総称が、筆者が提唱している「Ω祖型」と名付けられるべき象徴的図像の、通奏低音的な、最も普遍的な「イコン」なのである。
このΩ祖型は、轆轤で形作って焼いた素焼きのつぼによっても古代人の眼前に現れたものであり、それは壷という「道具」としての純粋な機能とともに、ある種の戦慄を呼び起こすものであった。何故ならその形状が「死のできごと」を連想させるものであったからである。道具が彼らの生活の利便に供し、それが彼らの生存を有利にしつつも、それ自体の成長と進化の果てに存るものが、「死のできごと」を引き起こすものと類似の形をしているという暗合は、きわめて象徴的である。これはヒョウタンを道具として利用するホピ族のようなアメリカ・インディアンの伝承の中にも、「灰の詰められたヒョウタンが頭上へ落とされる」という預言があることなどをわれわれに思い出させる。焼き物に限らず、ヒョウタンの実のようなモノを詰めるのに最適な原始的な容れ物が、まだ実現に至っていない「未来の道具」の形を伝えるための記号となっているのである。つまり、最も原始的な道具の原型とも呼ぶべきものの形状が、最も進化した究極の道具の形状と似ている*ということ。そしてその形状に対する元型的な記憶の共有が、文化的な記憶術を通して引き継がれているのである。
* 最も原始的なツールが最も洗練されたツールの形と類似しているという不思議な暗合は、S・キューブリックが映画『2001: Space Odyssey 2001年宇宙の旅』の中でも鮮烈に描き出している。映画冒頭の「人類の夜明け」と呼ばれるシークェンスの中に、われわれ人類の祖先となる類人猿の「ひとり」が、動物の骨を食料確保のために動物殺害のための道具として初めて用いたのち、それを勝利の歓喜とともに宙空に放り投げたとき、それが落下途中で21世紀の宇宙船に変容するというシーンである。



それにも関わらず、そうした記号的な意味を、その日常の必要から造り出した道具の中にも込めたのは、意図してでないということができようか?
壷は、今食する以上の量の(余剰の)生活の糧を貯め置くために現れた。したがって壷こそ、未来における自分たちの生存のために少しでも有利にするために製造された最初の洗練された道具のひとつと言えるだろう。そしてその《壷》は、象徴的なことに、文明というすべての事件の発端をもたらしたものであると供に、その終焉(あるいは救済)をもたらすものの形状をも予想する記号なのである。すなわち、余剰作物だけでなく、実利に資する道具という全ての元型的なものの《究極的な姿》をも詰め込み、その智慧のすべてをわれわれのために「貯め置く」ためのものでもあったのである。
■ 拙サイト内の参考文
金剛への第一歩──Ω祖型とは何か[2]