【映画】Crossing the Bridge - Sound Of Istanbul

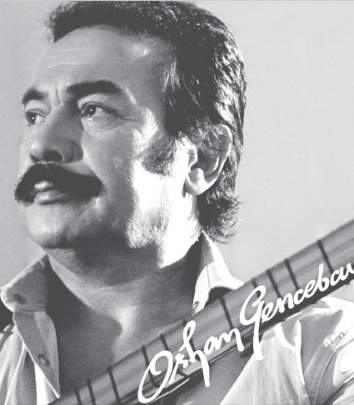
今夜は、『タッチ・ザ・サウンド』ではなくて、『クロッシング・ザ・ブリッジ』(サウンド・オブ・イスタンブール)だった。下高井戸シネマのレイトショーにて。内容はイスタンブールからの「今の音楽紀行」である。狂言回しならぬ現場の立会人・兼・飛び入り音楽家は、インダストリアル・ミュージックのハシリだったドイツの問題児バンド、ノイバウテンのベーシストである。だが、彼がそれ系の音楽家であることは、今回の音楽紀行にひとつの「傾向」を与えていることは確かだ。その視点は、「今のトルコの伝統音楽に何が起きているか」ではなくて、「今のトルコのミュージックに何が起きているか」なのだ。
私のトルコ音楽に対して抱いてきたイメージは、微分音と変拍子のインストの嵐、微分音を多用した狭い音域における歌謡、「どこを切っても同じ顔の金太郎飴」的な徹底して同じトーナルセンターを持った似たり寄ったりの楽曲群(でも素晴らしい!)、あるいはスーフィー系の旋回舞踊用の音楽などだった。今回の映画からその手の音楽が怒濤のように出てくることを期待すると少し肩すかしを食らうかもしれない。だが得るものは多い。「イスタンブールの音楽シーン」の現在と、「トルコの伝統音楽技法」というものがどれくらい急速に失われつつあるのか、ということについての証言にはなっているからだ。少なくとも聴きたかった種類のトルコ伝統歌謡は、もう86歳を過ぎた熟女が歌うばかりだと言わんばかりの作りになっている。
狂言回しに現地の音楽を体験取材をして回っていくという手法は『ブエナ・ヴィスタ・ソシアル・クラブ』にも通じる作風なんだろうが、作り手はいわゆる滅び往く(あるいは滅びなくていいが)伝統音楽の映像を伴ったアーカイヴ化に関心があるのではなくて、あくまでも取材対象の半分は、今の若い音楽家がどんな音楽を実践しているのか、そして彼らがどんな先達(音楽的巨匠)から影響を受けたか、という二面から描く。
だが興味深いのは、彼らが口で賞賛するほどには、音楽手法的にはそうした先達からの影響を受けているようには思えない位、すでに西洋音楽化していることで、彼らの楽器の使い方や歌唱法はきわめて急速に西洋音楽化しつつあることを物語っているように思える。したがって彼らが「影響を受けた」のは、そして自分たちがトルコ語で音楽をやるのは、多分トルコのソウルに当たる部分に触発されたからであって、決して手法的に伝統を維持することには軸足を置いていないことだった。
だが、考えてみればその現象はまさにわれわれの住む日本においてこそ顕著で、まさに我が身を振り返ったって、自分などは日本の伝統的手法や楽器には見向きもしないで、ピアノやオーボエなんぞを演奏するのを当然のようにやりつつ、酒席で北島三郎や森進一、そして八代亜紀の歌唱を賛美するのを肴に酒を飲んでいるのだった。そして日本のソウルはそうした人からの影響なのだ、などと嘯(うそぶ)いている。まさに人の振りをみて我が身を振り返るのであった。
(1ダース強のミュージシャンが出てくるが、そのそれぞれが日本のミュージシャンのそれぞれ誰に相当するのか、などと余計なことを考えながら観てしまった。あと、トルコ語のラップを聴いた後に、トルコ人の喋りを聴いていると、すべてラップに聞こえてくるのが、面白かった。われわれの「音楽」は、それを作る人の喋る言葉のようにしか作れないというある種の普遍性があるのだ。それが各国のラップから了解されるであろう。ベートーヴェンを聴くとドイツ語が聞こえるという人がいることからも、それは納得できる筈だ。)