読書録:J・H・ブルック著『科学と宗教』
読書録:J・H・ブルック著『科学と宗教〜合理的自然観のパラドックス』田中靖夫訳(工作舎)を読む。
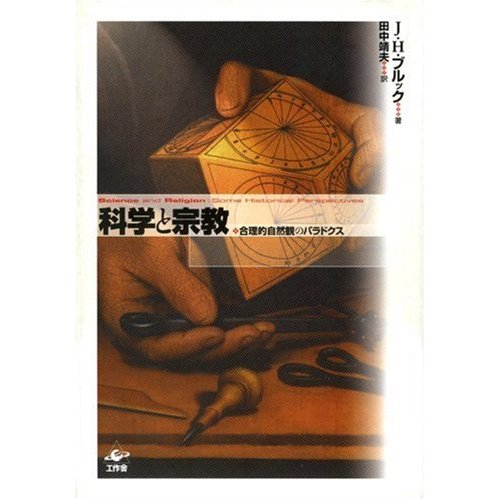
慧眼な読者は別のことにも気づかれることだろう。ビュフォンの連続する七つの年代と創世記の連続する七日との驚くべきアナロジー。反神学的でありながら、ビュフォンの視点には宗教思想の残映が認められる。彼の批判は科学と宗教が通約不能であるとする点で正鵠を突いていたが、相同性を利用したのはビュフォンの方なのである。
これは、何となく面白いと思ったので(と、言うより、今に重要な意味合いをもつことになりそうな根拠無き直感を得たので)引用しておいた。別段、ここでこの記述について論じようなどというわけではない。
さて、前回取り上げた『中世の覚醒』が12世紀以降の2,3百年の間に生じたアリストテレス哲学の自然観とキリスト教の宗教観の間の緊張感を描いた労作だとしたら、これは、科学と宗教が互いに対立・否定し合って発展したのではなくて、実はそれぞれが「互恵的」な関係の中で、つまり「たがいに助け合って発展した」のだという、一見驚くべき西欧の精神史をさらに長いスパンで追いかけた書物であると言えるだろう。
文章自体は訳文の若干の癖に加えて、内容の難しさも相まってなかなか頭に入って来ないところがあって読み進むのが難しかったが、『中世の覚醒』を読んだ頭で読んでいるので、科学と「人間の組織としての宗教」が互恵的であったということが、多くの証拠に基づいて論証されたのはよく分かった。内容的には実に価値が高いのだ。
こういう比較は得てして意味をなさないものと知りつつ言うなら、こうした歴史についての論述に対して、単なる興味以上の意味を見出そうとして取り上げるなら『中世の覚醒』は、非常にお薦めなのである。ひとつは、中世の覚醒の著者が、現代社会の問題なども考える思想家/活動家であるために行間に滲み出て来るうったえがある点で、こうした考察が現代社会の在り方を考える契機になるというのがよく伝わって来るからである。一方、この『科学と宗教』の方は、純粋に学術的なもので、ある種の学術的論争に対する備えとして厳密な議論を目指したという感じがある。
だが、こうした比較はやはりナンセンスであって、互いに持たないものを備えている点で、やはり「互恵的」なものなのである。
ニュートンに関する記述:
ケンブリッジ時代のある危機的な時期、彼は聖職の管理者から命じられた道義的な要求を甘受しなければならなかった。トリニティのフェローの地位を維持するためには、慣例に従い、聖職に就くより他になかったのである。それは国教会の定める三九か条に宣誓することを意味したが、彼の良心はそれを許さなかった。キリストが神聖を持ち、父とともに永遠であるという教義をすでに拒否していたからだ。(page 152「機械論的な宇宙における神の活動」より)
この苦悩というのは今を生きるわれわれの苦悩に似ている。
空間は、すべてを知って感じとる神、その下僕が叛くときを知っている神、彼自身が教会で林檎をつまみ食いしたり、安息日にネズミ捕りをこしらえたり、ケンブリッジ時代のルームメートにシラミのことで嘘をついたりしたこと、そのすべてを知っている神で満ちている、とニュートンは考えた。神の存在に関する強迫的な感覚は、彼が遺児であったことに由来すると心理学的には分析されてきた。俗界の父親を知らずに育った彼は、あらゆる絶対性が賦与された代替物を天上に見つけた、というのである。(page 153「機械論的な宇宙における神の活動」より)
ニュートンが遺児であったことは、初めて耳目にすることであった。基本的に自分は心理分析というものに信頼を置かないが、この記述にはある個人的な理由で関心を抱かざるを得ない。備忘録としてここに書く。
フランスの後世の世俗学者からすれば、ニュートンの宗教心は、要するに病気とされた。今日でも、古典力学の基礎を築いたほどの人物が、聖書の預言や宗教的な錬金術に凝っていたことは驚きの的になっている。歴史研究においても、特異体質でないとすれば前時代的としか言いようのない偏見を彼が持っていたのは事実である。例えば、異教の文明がユダヤ文明に先行したなどとは到底考えたくなかった彼は、ギリシア、ラテン、エジプト、ペルシアの年代記作者たちが「その初代の王たちを事実よりも少し古めかしている」と論じた。しかし、ニュートンは支離滅裂だったわけではない。彼の科学の特徴とされる合理主義は、聖書研究において欠如したどころか十分に発揮された。自然を解釈する規則を設定したのと同じ精神で聖書を正しく解釈しようとしたのである。崇高なる自負を持っていた彼は、確実な真理に到達することにより、自然哲学と聖書解釈の双方において、議論の余地をなくそうとした。(page 166「機械論的な宇宙における神の活動」より)
一八世紀はじめのイングランドにおける政治状況は、フランスと対照的(ママ)である。1689年の寛容令のもとで、国教会の三十九信仰箇条への署名などの条件を満たしさえすれば非国教徒にも宗教の自由を保証したからである。それでも不満の余地がなかったわけではない。非国教徒は宣誓令と地方自治体法によって教職に就くことが禁じられていた点で依然差別されていた。さらに急進的な非国教徒であるソッツィーニ教徒(キリストの神性を否定する)などは、良心ゆえに三九信仰箇条に署名できなかった。また、反プロテスタント勢力まで寛容政策を広げるのは、ローマ・カトリック教徒や無心論者をのさばらせるとして忌避された。(page 185「啓蒙時代の科学と宗教」より)
この「三九信仰箇条」について現在ネットで内容が読める。
英国国教会・三十九信仰箇条
英国国教会公式サイトに掲げられる「三十九信仰箇条:Thirty-Nine Articles of Faith」
他ならぬローマ・カトリックに対抗する英国国教会の宣誓文が「39か条」であったことについては、その象徴的な意味合いに思いを馳せないでいることはできない。
チャールズ・ダーウィンは、自らの生命観には壮大さがあると宣言して『種の起原』(1859)を締め括った。生命の力がいくつか、あるいはたったひとつの形態に「吹き込まれた」単純な始まりから、この上なく美しく、驚くべき生命体が進化してきたと。旧約聖書の喩えを用いたことや、「創造主によって物質に刻印された法則」に言及したことから、彼の結論に聖書風の宗教さながらの意義や価値観を読み取ることは可能である。彼の私信によると、そんなつもりはなかったらしい。植物学者のJ・D・フッカーに打ち明けたところでは、「何らかの道のプロセスによって出現した」ことの表現として、想像に関する聖書の言い回しを使って一般大衆に媚びたことをずっと後悔していたという。(page 300「進化論と宗教的信念」より)