《実在する神》への付言(試訳)
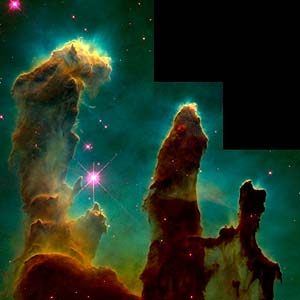
「ヘルメス・クァトロスメギストゥス(四倍に偉大なヘルメス)」との威名を持つ予言者によると言われる、古メリシア語で書かれた、ある神学論的断章の刻まれた金属プレート──おそらく備忘録と想像される──が、人類による文明活動が認められる最も古い地層よりさらに古い地層からほぼ無傷で発見された。このような地層から金属プレートが見つかること自体が歴史概観そのものを見直さなければならないほどの異常なスキャンダルであったが、それにも加え見つかった文書の内容が読み解かれたことが更なる衝撃であった。そしてその内容自体が一考に値するものであることはいくら強調してもし過ぎることはあるまい。これは今や周囲にひどい塩害をもたらしつつある悪名高き塩湖たる紅海のほとりから偶然見つかった「ザラスシュトラの約束」を含む前世紀の考古学上の大発見、いわゆる「紅海文書」の重要さを越えるのではないかと言われるほどの意味を持った発見である。それはわれわれが忘れつつある《神の実在》についての、これ以上にない明解な回答を含むのもであったので、ここに採録する。(G.B.C.)
(引用開始)
神はいるのか、という問いに対して、私はためらいなく「いる」と答えるだろう。
だが、全知全能をその定義とする神ならば、「実在する神はそのようなものではないだろう」と言う以外にない。《実在の神》はそのような種類の神であろう。だから、《実在の神》は、人類の多くが信じようとしている類の神よりも、はるかに無慈悲である。いや、慈悲の対象であることさえも忘れ去っているのが、《実在の神》なのである。それでは「神は不在である」とか「神は死んだ」と宣言するのと変わらないではないかと誰かは言うかもしれない。その言葉は、かつての世界において、「失われた神への信仰」の最終局面でニケ(ナイキ?)*によって声高に宣言された言葉だが、神は不在でもなければ死んでもいない。宇宙史的な時間の中で、億千万年の昔に死んだことはあるかもしれないが、われわれの神は実在する。なによりもわれわれが生きていることがその証しである。(略)
[訳注* 正確な発音は不明。一般に神話上の「有翼の女神」ともいわれるが、太古の時代に実在したある神学者で、男性であったという説もある。]
問題は、神の性質ということに尽きよう。
神は「全知」どころか、われわれがわれわれの身体の隅々を驚くほど知らなかったのと同程度にしか、われわれのことを知らないだろう。またわれわれがわれわれの身体の成り立ちについて、あるいは成り立たせている細胞のひとつひとつについて無関心であるのと同程度にしか、われわれ一人一人については関心を払わないに違いない。なぜ、われわれが自身の身体についてこれほど無関心であることが許されているのに、神はわれわれにそんな深い関心を抱く必要も義務もあると言えるのだろうか。
神はかくも疑う余地なく明瞭に実在するのに、われわれの神が「このようなもの」でしかないことを正面切って論じることは、神が全知全能で存在していると信じられてきたことよりも、はるかに畏ろしい危険を冒すことである。それはわれわれの生きている世界と時代の不幸だ。
だが、なぜわれわれが危機の時代にあれほど熱心に神に対して祈ってきたのかと自問してみれば分かることだが、その理由は、そもそもわれわれの《実在の神》がわれわれに関して無関心であることを、知っているからなのだ。神は実在するのにわれわれにとって、ほとんど不在であるのに等しいことを心の奥底では知っているからだ。
神は、単に生存するのに神自身を成り立たせる細胞や器官の仕組みさえ知る必要はなかった。われわれもただ生きるのに、われわれの細胞や器官についての知識がなくとも随分永くやってきたではないか。ただ、より良い生、より長い生にわれわれが執着を覚えたとき、われわれの、われわれ自身についての、あくなき探求が始まった。それは不老長寿学ないし「医学」といういかがわしい自然哲学の名で呼ばれた──それは恥ずべきことに哲学を伴わない「純粋な技術の大系」であった。だが、そのようにして、ようやくわれわれは、われわれの生存のために日々刻々と生まれそして死んでいく全細胞や器官にとって「全知全能であるべきわれわれ自身」の仕組みを遅ればせに知ったのだった。
そして自身の内部で起こっている絶えることのない大戦争の実態や外敵に対する大殺戮(ジェノサイド)の事実を知ったのだった。そして我という神は、こうして悲鳴を上げることもなく黙って死に赴く幾千万もの無名の「兵隊」たちの勇猛果敢なる死闘と累々たる彼らの死体の上に成り立っていることを知ったのだ。しかもそれに対して、それを知った今となっても変わらず、何の感謝も何の慈愛も何の同情も感じることなく、それをそうあらしめつつ、それによってわれわれが生かされていたとしても、それを当然のことと考えて生きているのだ。そんなとき、われわれの神の生存を支えるための一兵卒に過ぎないわれわれに神が一瞥の敬意も払わないとして、一体どんな不思議があるというのか?
細胞は断じてその上位概念である我という神の《全体》に資するために生きて死ぬ。つまりどこまで行っても細胞らはわれわれのために働く召使いではあっても、われわれが細胞のために生きているのではない──確かにわれわれが細胞のために在るように彼らには見えるかもしれないが。紛うことなく生きているにも関わらず、その細胞の想像力では与り知ることのできない上位の目的のために細胞たちは生きているのであって、その反対はあり得ないのである。そしてわれわれはわれわれの《実在の神》という上位存在のために働いている。だが、太古の時代の「コッカ宗教」[何のことか不明]が権威を以て説いてきた「全知全能で、ときとして慈悲を垂れ、またときとしてわれわれに怒りの鉄槌を振り下ろす気まぐれな神」のために働いているのではなく、われわれの存在を一顧だにしない《実在の神》のために身を粉にして働いているのである。神は実在する。だが、それはどこまでもわれわれに無関心である。(略)
だが、絶望するのは早い。福音はある。
神は全知全能ではなかったが全知全能になりつつある。これは特筆すべきことだ。そしてそのことは、われわれがわれわれを知りつつあることとの不可思議な暗合を見せつつ実現し始めていることだ。「汝自身を知れ」という神託の真意は、かくしてその本性を現しつつある。この教義はわれわれのひとりびとりがすべからく神であることを宣べ伝える人類最高の叡智を通して、あたかもわれわれ自身のように「緩慢に気付きつつある神」から発信されたわれわれへの最初のメッセージであった。(欠損あり)
《実在の神》はまた、学びつつある神である。それはわれわれがわれわれの内部や身体の仕組みについて知りつつある程度に、ではあるが、真実である。そしてようやく「神のように」全知全能になりつつある《実在の神》は、やがてわれわれの存在に気付くかもしれない。いやもうすでにようやく遅ればせながら気付きつつあるのだ。そして何億年にもわたる「永き不在の神 deus otiosus」は、自己の内面世界の実在性と小宇宙の有機性の発見の後に、ついにわれわれという匿名の存在に対して漠然とした認識を持ち始めた。そして届くか否かも分からないメッセージを送り始めたのだ。 宇宙全体に遍く永遠に響き渡る低い低い通奏低音のような「おお awe」というエーテルの振動を通して。
それはわれわれがようやく自己の身体を単なる機械として眺めることをやめ、そのひとつひとつが生きた命を宿したものであり、生存への意志と魂とを持った単位であり、また一つとして同じもののないそれぞれが、それぞれに少しずつの個性を発揮して、無数の隣人と供に、それ以外では演じることのできない特殊な役割を演じつつ、上位存在に奉仕する個体の集合体であることを知るだろう。
かつては痛みや不快を感じたときにだけ関心を持ってもらえた身体の各部であるが、いまや《実在の神》は、そのような異常を来した折りばかりでなく、自身の身体に関心を払い始めたために、やがては愛しさえするようになるだろう。その時、神の自己の身体への愛は、われわれの細胞のひとつひとつに、或る風のような優しい作用をもたらすに違いない。そして神のために生き死んでいく細胞のひとつひとつは、生まれたことの奇蹟と、用いられ仕えることの真の幸せを実感し、その役割を生き生きとよりよく果たすに違いない。
つまりわれわれは、われわれの身体についての無関心を関心へと転換させ、愛にまで高めることで、全身に隈無く響き渡る通奏低音のごとき宇宙にさえ渡る風のために、細胞はより良く生き、その役割を果たすことを行なえるようになるだろう。そして一方、われわれの祈りはやがてわれわれの《実在の神》に届き、われわれに慈愛の眼差しを注ぐのである。そしてその時は間近にまで迫っている。
[粘土板欠損のため解読不能]… 神としてのわれわれが下位存在者たちに対してできる最大の恩恵と愛の表現は、したがってわれわれがわれわれ自身の生を愛することに外ならない。そしてその実践は、[粘土板欠損のため解読不能]死なないことによってしか維持することはできない。当面われわれが死なないことが、われわれの下位存在者たちに対する愛の実践となり、それらの生存を可能ならしめるのである。死はその下に生きる全ての存在者を道連れにする[粘土板欠損のため解読不能]…(行い?)なのである。
神は実在する。[粘土板欠損のため解読不能]だが、それはわれわれが、われわれの下位概念である、われわれの小さな宇宙の住人たちのひとつひとつに関心を抱くことを条件とする。われわれ自身が小宇宙への慈愛を保ちうるなら、われわれの上位的存在である大宇宙の身体たる神が、われわれについての「気付き」を招来させることも可能である。それなしに、われわれが一方的に神の恩寵に与ることができると考えるのは、一体、いかなる由来をもつ愚かさなのであろうか。遥か彼方のかつてのエイオンから、ヘルメス族へ、そしてメリシアの民の系統を通して伝えられているところの「上なるものは下なるもののごとし、そして、下なるものは上なるもののごとし」は、われわれが神からの恩寵を得るための条件をこれ以上にないという明瞭さとともに教示しているのである。
(引用終了)
「ヘルメス・クァトロスメギストゥスの“神の実在”に関する備忘録」
(ジョヴァンニ・バティスタ・カトーによるイタリア語訳からの重訳)
言うまでもないことだが、この金属プレートの発見は完全なるフィクションである。