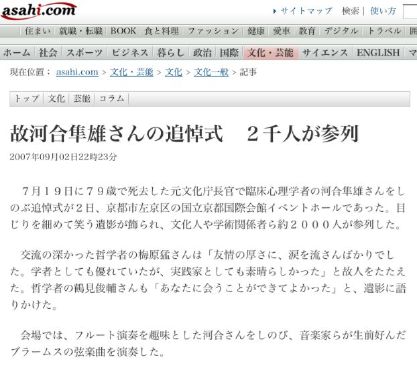まず前提を理解しなければならない。ユングは全体主義的な哲学とは縁もゆかりもない。彼の根底に流れる通奏的な思潮は、むしろ「反近代」とさえ呼ばれるに相応しいものである。
欧州大戦中にナチズムに加担したということが言われるユングであるが、以下のようなユング自身の記述から伺い知れるのは、そうした全体主義的な時代精神というものに対する、むしろ批判と嘲笑なのである。
ウィルヘルム一世の戴冠式がヴェルサイユで行われたというニュースを聞いたとき、ヤコブ・ブルクハルトは「それはドイツの破滅だ」と叫んだ。すでにワグナーの諸元型が扉を叩いており、それとともにニーチェのディオニソス体験があらわれた。それは陶酔の神、ウォータンに帰するものという方が良いかもしれない。ウィルヘルム時代の傲慢はヨーロッパを不和にし、1914年の惨禍へと道を拓いた。
(ヤッフェ編『ユング自伝・2』みすず書房 page 50)
彼はそうした時代精神が怒濤のように流れ始めていることを肌で感じとってはいたし、そのことの「意味をよく理解していた」が、彼の時代に対する眼差しはむしろ客観的である。例えば、次の記述は国家主義というものの本質を見事に捉えていて、自由主義という名の下に国家への隷属は強化されるのだという、今日においてさえ重大な警鐘となることを述べている。
輝かしい科学的発見によってわれわれは恐るべき危険にさらされていることは言わずもがな、大いなる自由という希望は国家への隷属の増大によって帳消しされていることを、認めようとはしない。われわれの父や祖父たちの求めたものを理解しなければ、それだけわれわれはますます自分自身を理解しなくなる。かくして、われわれは個人としての根源と、自分を導く本能とを断ち切ることに全力をあげて加担し、その結果ニーチェが「重力の精神」と呼んだものによってのみ支配される集団の一分子となるのである。
(ヤッフェ編『ユング自伝・2』みすず書房 page 52)
■
などと、引用しながら『ユング自伝』を楽しく通読していたら、先頃死去した故河合隼雄の追悼式があったという報道が入って来た。
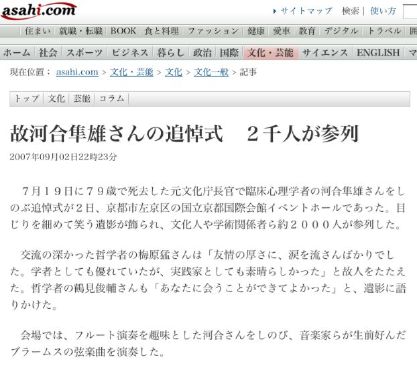
死者に鞭打つようだが、彼の業績についてはユング紹介者・翻訳者・研究家としての側面しか評価することはできない。
それにしても何ゆえに、晩年の河合隼雄は国家権力のこういうしょうもない手先みたいな輩に成り果てたんだろうか。いわゆる「知識人代表」として、文化庁の長官を務めた後、文科省文責の悪名高き“道徳”の副教材『こころのノート』の編集に積極的に携わるなど国家官僚的なエリートとして終わったということは、アカデミックな人間の極めることのできる頂点のひとつであって、世間における“成功”の一例なのだろう。だが、これはまさに生前のユングが背を向けたことではないか。そして彼の周りにいたよき理解者らしい知識人たちは一体彼のそうした奇行をどのように眺めていたのだろう。それが不思議でならない。
『ユング自伝』によれば、ユングは常に悩みながらも内なる声を意識化することを心がけ、内面の心の力と向き合った。また自己#1と自己#2の間でそのバランスをとり、ふたりの自分の間の矛盾に自分なりの折り合いを付けた。
それに対して、日本におけるユング紹介者・河合隼雄は、晩年、国家(権力)としての日本の、国際競争力と未来において「闘争し勝ち残れる子供たち」の製造に心血を注いだ。これは彼の業績の中で、掛け値なしに恥ずべき汚点だ。道徳教育の全面的な復活という最終目標が持つ意味について、彼が十分に深く考えたとは考えにくいほどの浅薄な懐古主義と呼ぶべきであろう。
河合隼雄がアカデミーの中で成功していくうちに、だんだんと国家権力側の方に取り込まれていったと思われる軌跡は、彼の著書の出版社や共著者の面々から見ても伺える。岩波や朝日新聞社などから刊行された本は多く、共著者としても、鶴見俊輔、大江健三郎、谷川俊太郎、村上春樹、山田太一、中沢新一、鎌田東二などの諸氏がいて、彼らが河合隼雄の、後の時期における国家権力への偏向(否定し難い権力志向)は誰にも予測できなかったのであろう。
河合隼雄のそうした偏向は『モラトリアム人間の時代』を書いた小此木啓吾との交流辺りから出てきたのではないかと推量する。小此木啓吾のモラトリアム人間についての論理が何を導くために意図されたのかは分からないが、「国民」が国家にとって有用な労働力であるべきだという権力/国家中心的な視点に力を与えることになったのは確かである。いずれにしても河合隼雄は反全体主義や反戦思想を持った知識人との交流を持ち、共著の多くをそうした人々と協同して出版することでキャリアを始めたが、最後は極めて国家主義的・全体主義的・反動的な思想を述べるスポークスマンとなった。極めて遺憾なことである。
一方、日本ではユングについて語ることは、その思想の初期の紹介者であり数少ないエラノス会議への日本人参加者の一人であった河合隼雄を、不幸にも連想することなしには行なうことができない。河合隼雄の晩年の国家官僚としての奇行は、ユングについて語り論じるとき、確実にわれわれに困難をもたらすだろう。
ユングの元型論や集合的無意識論というものが、河合隼雄が与したような全体主義や国家主義(自己の優先的生存)へとわれわれを駆り立てるような論理を本質的なものとして含むものではないにも関わらず、そのようなものである印象付けが、正統で余りある良心的な反・河合論者の側から成されつつあることが、実に残念なのである。ユング理論と晩年の河合の道徳論とは、明確に分けて論じる必要がある。
それにしても、日本ユング研究会会長をやっている林道義をはじめとして、日本におけるユング派がどこか「ロクでもない人たちの集まり」であるようにも思え、不信の念を拭えないのである。
「河合憎ければ袈裟(ユング)まで憎い」式のユング批判もある。主張の中心にはむしろ共感するが、こうした研究者によって河合批判のみならず、ユング批判にまで及んでいくことは、今後その批判の矛先が自分にまで及んでくる可能性を暗示しているので、時間を掛けて思潮の整理と我らが理論の強化をしなければならないのである。
参考サイト:続・日本ユング派 河合隼雄批判