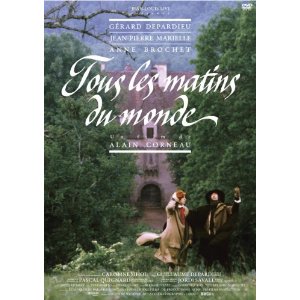「小沢一郎は勝つのか?」と題する、政治にきわめて密接に関わりのある発言を内田樹氏が行った。
その中で氏がさりげなく語っている「小沢の持っているカードのひとつ」、すなわち「対米強硬姿勢を実現するかもしれないという田中角栄の日中共同声明以来の外交的期待」については、実は国民は知らなさすぎるというのが自分の考えだった。だからもっと知らなければならない、とずっと思っていた。なんで田中角栄が逮捕されたのか、どうして小渕が、橋本が、現職の総理や議員が、かくも多く憤死していったのか? そして、どうして鈴木宗男や佐藤勝が裁判にかけられたのか、そしてとりわけ政治家・鈴木宗男に関してはどうしてこのタイミングで司法判断が下るのか、こうした諸々の理由を知らなすぎる。それで自分は微力ながらも想像力の透視できる範囲で、自分の世界観を語りもし、必要な文章の紹介もして来たつもりだった。
だが、この本当のことが、民意として意識化され、顕在化された暁のことを、そしてそのことによって惹起されることの内容を、われわれはまだ知らない。
この認識が当たり前のこととなって、当然のように国民の口から漏れ聞こえるようになった時とは、日本における反米を基軸とする《真の》ナショナリズム復活の到来を意味する。
だが、筆者はナショナリズムだからと言ってそのこと自体に性急な価値判断を下す意図はない。否定されるべきナショナリズムと否定し難いナショナリズムとがあるからだ。筆者が反対するのは、アジア諸国など、かつての日本の植民支配をした地域に対する相も変わらぬ優越感であり、それに根ざした日本の選民意識といった低級な形態のナショナリズムであり、あるいは日本人を低級な民族であると無意識に考える(そして原爆投下さえも正当化できると考える)欧米の支配階級にある優越意識である。ひとつの利益を共有するべき集団(国家か民族かは問わない)が、一方的に他の国家の国民(民族)や政府(支配階級)によって収奪され続けることに対する当然出るべき反対の声を、そうしたネガティブな「ナショナリズム」とおなじレベルで判断されるべきだとは思わない。
どこかでも一度書いたが、民族や国家意識というものは、そもそも最初から(アプリオリに)在るものではなく、「叩かれて、支配されて、そして財産を奪われて」初めて生まれるものである。「おまえはダメだ」と言われ続けて、自分を愛する気持ち(自尊心)が反動として発生する。愛国心も同様で、くだらぬ愛国心教育によって生まれるものではない。まさに、日本でそうした意識が生まれるのだとしたら、それは歴史的必然として、被支配者が、不当な支配から逃れようとする運動から生まれるのである。そして、それが日本で誕生するのだとしたら、それは明治維新前夜の攘夷思想と同じ、「お家」に関する危機意識(今回は実際の非支配の認識)からであり、それは幕末以来の本当のナショナリズムにまで育つ可能性のある大きな芽だ。つまり、そもそも無くてもよかったそんな(国民/民族)意識を、むしろ「宗主国」であり支配者である合州国は、力を行使することで自らこの地で目覚めさせようとしているのだ。
先にそうしたナショナリズムを、《真の》と断らなければならないのは、日本における今日の(そして60年続いている)「ナショナリズム:国家主義」は変な捩れを起こしていて、よく街宣車で見かける日本の「いわゆる右翼」は、対米従属の「右翼」(反共である、という1点においては「右派」であることは確かだが…)であって、戦後アメリカべったりになった日本の「国体」を、そしてアメリカの国益を守る圧力団体(基い、暴力集団)なのである。これは本当の国粋主義者らが、米帝からの自主独立を叫び始めて本来右翼がどうであるべきかの手本となるべきところを、却ってその奇妙な行動によるネガ・イメージによって、われわれの関心をナショナリズムの真の目覚めから逸らしているのである。
一方、ひるがえって日本の左翼は、本来なら日本の自決をもっと本質的なところで説かなければならないところを、自民党の多元外交派も一元外交派も十把一絡げにして批判・否定することで、本来的な日本の国益になるべきところを損ない、却って、「左派」でありながら米帝国の国益になるような手助けを知らず知らずに行っていたりするのだ。これは明確に《反米》を旗印に掲げる極左のことではなく、いわゆるゆるやかな正義派・社会派の左派議員(社民党に見られるような)に著しい。それは「政治とカネ」の腐敗を糾弾する正義の意図で行われることだが、日本の国益を考えている政治家の失脚などのための材料を各方面に提供したりすることで、知らず知らずに起きてしまうのである。残念なことだが…
話がそれた。真のナショナリズムの復活がいよいよ明瞭になって来たとき、この国を実質的に支配する合州国がそれを放置するだろうか? もちろん、これまでも放置しなかったし、これから先も放置することは無いだろう。それが角栄の逮捕であり、そして多くの多元(非米)外交派に対する政治生命断絶の工作であった。そして現在も進行しつつある「東京地検」など、「恐怖の名」で知られる法曹界からの起訴/裁判による暴力である。つまり、この圧力や工作はいよいよ猛威を振るうだろうし、ひとが本当のことを知ろうとすることに対して、一層の情報攪乱を行うだろう。つまり、そうした日本人の目覚めに対して、目覚めないようにさらなる不可視の施策を行うとともに、実際に止められない目覚めに対しては、目に見える脅威を与え始めるだろう。
(つい先だっても小沢が力を振るおうとしたときに、日系自動車会社のリコール問題が噴出した。これは「空爆」の新たな形態である。経済爆弾を落とすのである。)
目に見える脅威としては、反米ジャーナリストや研究家、大学教授などの発言力を持つ人間(情報発信者)の冤罪事件の頻発、裁判の長期化による社会的影響力の削ぎ落とし、などがある。裁判所による判決の前に、裁判沙汰になったり被疑者になっただけで社会的な制裁が実質的に行われてしまう日本の土壌(というよりは日本のメディアの体質)では、容疑人となっただけで日本ではアウトである。有罪であるか否かに関わらず、「世間をお騒がせ」しただけで、日本では制裁の対象となるのであるから。
だが、問題はこうした各種工作にもめげずに行われる日本人の目覚めへの方向性は不可逆であることだ。どんなに時間が掛かってもその抵抗は続けられ、遠からず他国の権力者による支配は終わりを告げるであろう。あるいは、全面的な暴力的な闘争へと発展するだろう。本当のことを知った日本人がマジョリティーとなった日本は、抵抗勢力(レジスタンス)の地下の牙城を築くかもしれない。
われわれは、今日、数少ない《知る側》に属するマイノリティではあるが、その認識が一般化した時のことをありありと心に思い描くことができるだけの洞察力も同時に培う必要がある。そのときに起こるべき「敵」の「抵抗」が、どんなシビアなものになるかを含めてである。
われわれは目覚めずに、働き蟻のように捨てられるまで他国の利益のために働き続ける方が良いのであろうか? そしてその働きは自分たち(国民の)利益のためにあるべきだ、という当たり前の主張が通るような世の中の実現を、諦めるべきなのか? それを自らに問う必要がある。