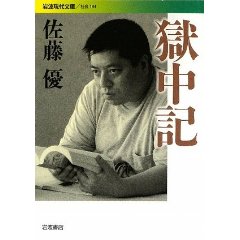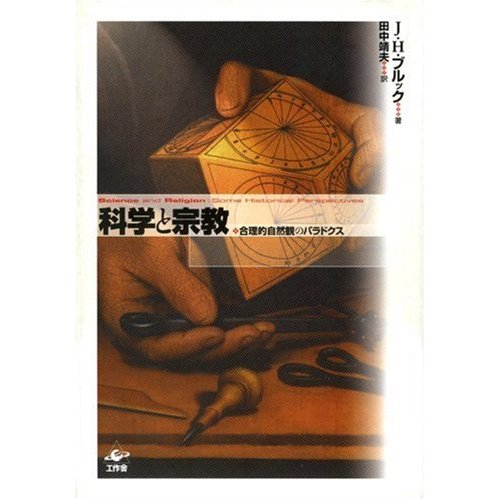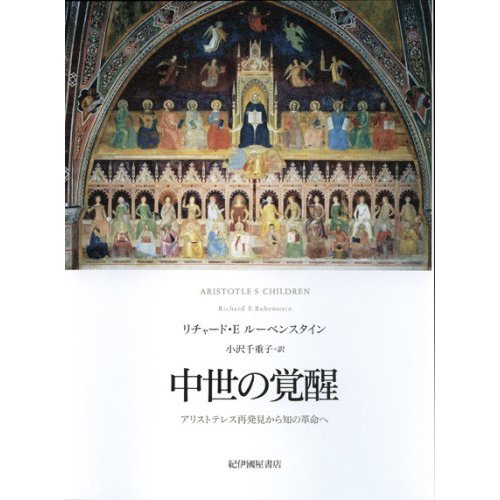ゲームを着想し、カタチにしたFriedemann Friese氏にまず敬意を。
作品を世に問うたパイオニア精神は評価されるべきだろう。持ち上げて突き落とすみたいだが、たとえそれがゲームであれ、世に問うた限りは批判も受け付けなければいけない。3週連続でワイワイ実際に遊んでみて感じたボードゲーム『電力会社: Power Grid』の《穴》について書こう。
まず、大大前提から。このゲームには「電気を売って、ガンガン儲けて、目指すは金持ち、電力長者」というコピーが付けられている。実際にはここまで単純ではないが、このゲームの本質を言い得ている。正確には「一番多くの街に電力供給できた」経営者がゲームの勝利者だが、ゲームの「上がり」が一番儲けた参加者であることに違いはない。これが実はすでに過去の価値パラダイムに属した経営理念だ。「一番社会貢献をした企業が勝ち」とか「一番環境インパクトの少ない商業的成功が勝ち」とかという設定だって良いはずなんだが、やはり「一番多く売り上げた」、つまり「儲けた者が勝ち」なのだ。
(この「資本主義的現実」は、「現実」として受け入れなければならないとしても、その資本主義の論理が、永久には持続できず(戦争などのリセット劇を挿入しない限りは)どこかで行き詰まるという点では、近い将来その徹底的な敗北が約束されている論理だ、とか何とか色々言えるのだが、論点が外れるのでこの点については深入りしない。)
いずれにしても、この価値観はメガトレンド的に逆行している。つまり「一番儲けたのが勝ち」なら、極論的には何をしても良い、どんな社会的無責任も関係ないということである。これはゲームの前提としては《穴》が大きすぎる。
例えば、資本主義的経済が現実であるのなら、「原子力発電のコストが一番安い」というのは、もはやまったく現実味がない。原子力発電を選んだら絶対に避けて通れない廃炉の問題。万が一(と言うか、現実に進行中なのだが)、事故が起きた場合の補償の問題。などなど、加味し始めたら安いなんてことはあり得ないことが、現実には分かっているが、それはおそらくゲームが想定している「安い原発」という抽象的な観念の中には入っていない*。
* ファクトとしても、例えば日本では1基たりとも成功裡に廃炉までこぎ着けた原発は存在しないし、仮に元あった場所から原発を跡形もなく無くしたとしても、廃炉に伴って大量に発生する高レベル放射性物質の最終廃棄処理をする場所さえも決まっていないし、それによって生じる(取り返しのつかない)作業者の被曝についても想定されていない。つまり捨て場のない猛毒のゴミが、処分地もないままどんどんできていくという、「トイレのないマンション」と揶揄されるに値する現実に対して、コストどころか、現実的な解決策さえも見えていない。つまり、お金では買えないファクターが介在しているのだ、この「原子力発電所の処分」という問題には。
原子力は火力発電に置き換わると夢見られたらしいが、実のところウランは極めて埋蔵量が少ない希少な燃料であり石炭や石油よりも早く枯渇する。一方、通常の原発から出てくるプルトニウムを使った高速増殖炉は、まだ商業的運用に成功した例自体がこの地球上に存在しない。(ちなみに、このゲームを紹介してくれた川田十夢さんが「プルトニウム」とTV Brosで書いていたのは、おそらくウランのこと。)唯一未だにその道を探っている日本の《もんじゅ》も、動かすことも廃炉にすることもできない非常に危険な状態で止まったままである。それをごまかすためにプルサーマルなる全くデタラメな使用法(要するに、使い道のないプルトニウムをちょっとだけウラン燃料に混ぜる)を行い、原発の危険性と毒性を上げている。つまり「安いプルトニウム」が、どんなに無尽蔵にあっても、それを利用する手段さえわれわれはまだ持たないのだ。つまり、そんな燃料を使うことを前提としているゲームとは一体なんなのか、ということだ。
そして、もうひとつの《穴》は、自分が拡張した供給ネットワークを維持するのに必要な電力量より、実際供給できる電力供給量が下回った場合、単に「儲けが少なくなる」ということだけでいい、とされていることだ。これはにわかには受け入れがたいルールだと感じる。供給量が需要を下回った場合、現実的には大停電が起きる。拡張した以上は、絶対に供給を持続するというルールにしないと緊張感もなく、ゲームとしてつまらないではないか。供給できなかったらその街は他のプレイヤーの手に落ちるとか、街の工場から訴えられるとか、銀行に抵当として取り上げられるとかのペナルティは無いのか? これが無いのだ。基本的にペナルティがないゲームなのだ、《電力会社》は。現実社会では沢山ペナルティがあって、それを避けるために企業は戦々兢々としながら企業経営を続けているのに。
最後に言及したいゲームの《穴》は、現実の世界(というか日本)では電力会社は自由競争に曝されていない点である。国内では1地域に付き1業者(ヨーロッパは知らないが、アメリカもそう)というルールの中で会社経営が成されており、東電も東北電力も中部電力も関電も、競争相手など、「いない」のだ。だから、「一番低コストの発電方法」を追求する動機そのものが存在しない。どんなに電力が高くても、この業者から供給を受けるしかないのだ、われわれは。現実世界では、このゲームの提供するような緊張がない。現実ではこのゲームのような健康的な競争原理そのものが働いていない。ことによると、このゲームから現実の方が学ぶべき唯一の点は、このことに尽きるのかもしれない。(おっとこれはゲームじゃなくて現実に対する批評になってた。)
それでもこのゲームはゲームとしてはそれなりに面白い。頭も使い、計算も必要。しかし逆に言うと、「計算だけのゲーム」とも言える。所持金、発電所代、燃料代、街の建設費、収入という5つの数字の加減だけでゲームできる。リスクや事故などがない。人生ゲームやモノポリーにだって沢山アクシデントがあったような気がする(病気や遅刻で1回休み、とか借金とか)。足し算と引き算という会計士みたいなセンス、そして競りでブラフを使うセンスがあればこのゲームに勝てる可能性は高い。
オークションという不確実要素はあるが、罰ゲームカードを引くとか、骰を振る、というような偶然によって自分の運が変わるというゲーム性がこのゲームには薄い。現実の人生は運・不運の類が渾然一体となって折り重なっている。つまり、ゲームを現実に近づけるもっと大きな要素とは、チャンス(偶然)やアクシデントの要素である。
現実社会では風の吹かない週があり、需給バランス以外で起こる原油価格の暴落や高騰(などの権力者による操作)がある。CO2を下げよという「議定書」からの圧力があり、また環境圧力団体からの脱原発運動があり、さまざまな原因による「事象」がある。こうしたことが、それぞれの発電システムにふさわしい形で襲いかかってくるのが現実だ。だから、このような「チャンス/アクシデント」カードのようなものがあれば、このゲームはもっと面白くなるだろう(すでに難しいゲームのルールが堪え難い複雑さを呈するだろうが)。
このゲームはこうしたチャンス(偶然)の要素が無くても十分に複雑である。マニュアルが手放せない難しさだ。それをさらに難しくする方向だとは分かっているが、ゲームをやりながらもっと複雑にしたい誘惑は抗しがたいものがある。
したがって、大きなリバイズとアップグレードを必要とする余地のある、発展途上のゲームであるという評価は、やはり甘んじて受けねばなるまい。そのためには、ゲーム制作者は「一番儲けた者が上がり」などという愚かしい前提の克服から、まず始めなければならないのだ。
最後にこれを紹介してくれた川田十夢さんに感謝。
この投稿は 2011年6月24日 金曜日 01:09 に Good/Bad Books Memo, Other people’s blogs, Politics! カテゴリーに公開されました。 この投稿へのコメントは RSS 2.0 フィードで購読することができます。 コメントを残すか、ご自分のサイトからトラックバックすることができます。
コメント / トラックバック1件
 Photo:
Photo: