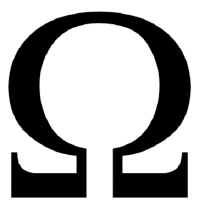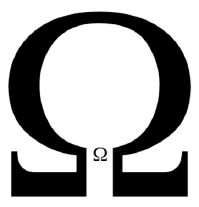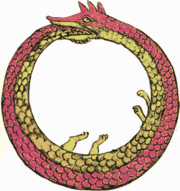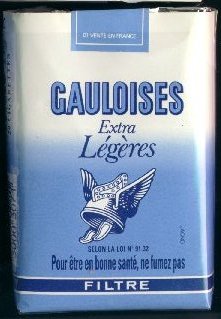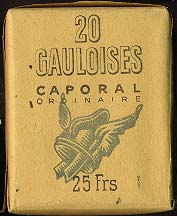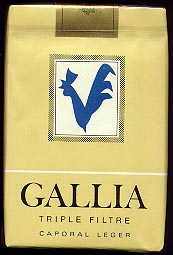G・ファン・デル・レーウ『宗教現象学入門』を読む #4
Friday, March 26th, 2010
第二の種類の聖なる行為で、多くの宗教できわめて重要な役割を演じているのは、供犠である。ここでは、浄めの場合のように、力との接触を持ったり、断ったりすることだけが問題なのではない。供犠はさらに進んで、多くの場合、人間に直接に力、神的力を所有させる。(中略)
頻繁に用いられる説明は、神が私にお返しをしてくれるよう、私は神に犠牲を捧げるという、ギブ・アンド・テイクの考え方による説明であり、供犠は贈り物とお返しの体系をなすことになる。多くの供犠が、これやこれと似た考え方から説明できるのは、全く自明のことである。しかし、ギブ・アンド・テイクの公式が、供犠一般の心理学的根拠を説明できるわけではない。(中略)これを一般的で本来的な動機として持ち出すことはできない。供犠が本来は打算以外の何ものでもないとすれば、最も初期の諸宗教現象は何ら宗教ではないであろうとジェヴォンス[1858-1936、イギリスの宗教学者]が言ったのは、全く正しい。(中略)
誰かに何かを与えることは、未開人の思惟では、われわれにとってとは別のことを意味する。贈り物は、それをもらった人をただ好意的な気分にさせるだけではなく、呪術的な意味でその人に「働きかける」。考え方や言葉と同じく、贈り物にも強制力があるわけである。(中略) 贈り物、供犠は「力」の給付である。多くのマナを持っている王が、そのことを示しており、王は多くの贈り物をすることで、それを証明する。(中略) 何かを振る舞うことは、力を流動化することを意味する。供犠と金銭(Geld)は、その起源でつながっている。古代高地ドイツ語で供犠という単語は「ゲルト」(gelt)であった。金銭は供犠の供物として、神聖な起源を持っているのである。未開人の贈与から、一方では神聖な活動である供犠が、他方では世俗的な活動である商業や金融業が発達した。贈り物に「価値がある」(gilt)とは、力を呼び起こすという意味である。北アメリカの「ポトラッチ」のような風習、つまり互いに競って一見無意味な浪費をし、価値あるものを破壊することもここに由来する。
「神と人間──聖なる行為──」(の章)より、「A 外的な行為」の「26. 浄化、供犠、聖餐」より(page 201-203)
浄化と供犠が同列に論じられる場面とはそもそもどういう場面だろう。犠の字面からも想像できるが、「供犠」には生き物の血が流されることが多く、それはむしろ土地を血で汚す事態であるとさえ言えるのであるが、ここにも典型的な「反対物の一致」の範型が見出されるのである。血を汚れたものと考えるのは、流される血が身内(仲間)のものなのか、身内外のものなのかなどの視点の遷移によっても自在に変わり得る。また、血を流す目的によってもそれに賦与される価値観は多様であり得る。
また血を誰が流させるのか、誰が供犠として「生きていた者」を死者として神の元に「帰す」のかによっても、その流される血の性質は変わる。供犠の供物として選ばれるのが、世界を不浄のものにしている邪悪で俗なる存在であれば、それを殺害し、供物として神の元に「帰す」のは善なる行為と本人たちによって位置づけられるであろうし、その血によってこれまでの罪過は購(あがな)われ、打ち消されさえするであろう。そのような「血」であれば、この血に「浄化する力」があると理解されても不思議はない。
だが、レーウ自身も強調するように、「浄化」という言葉の、われわれが連想しやすい表面的な部分に捕らえられてはならないという面も同時に存在するのである。浄化は、すなわち旧い世界の更新、そして新たなものを生み出すための儀礼的な動作でもあり、「モノや場が祓われてきれいになる」ということとは別次元の意味があるのである。もっと具体的には、邪悪なものがこの世から一掃されるという事態は、「世界が浄化された」と捉えられたとしても何の不思議はない。つまり敵の血は不浄のものであると同時に、それが流される時は世界を浄化する契機となる両義性を持つのである。
われわれの生きる現代という時代においても、このような「供犠」が実際に行われたことは記憶に新しい。それはきわめて宗教的な用語——ホロコースト——で呼ばれているジェノサイドである。それが「世界の浄化」というような位置づけと規模とを以て行われようとしたことは特筆すべきであり、それが宗教的な儀式の体を成していそうな側面について、われわれはもっと注意を向けても良いだろう。むろん、この用語の定着が比較的最近のことであり、またシリーズ『ホロコースト』のようなテレビ作品がその役割を担ったことは疑いがないものの、その後それが特定の歴史的事象を表す固有名詞として定着したこと自体が、件の事件をそのように捉えようとする事前の心理が働いていることは少なくとも認めることができよう。
ご存知のように、その規模や組織性については未だ諸説あり、その歴史的事実を巡ってさえ未だにその真相が解明されていない面があるという主張もあるそうだが、本論において、こうした政治的な動機に突き動かされた恣意的な歴史決定に関して、われわれは口を挟むべき意見を持たない。だが、第二次ヨーロッパ大戦の最中に行われたユダヤ人の大量虐殺が、現在、「丸焼きの供物」を意味する「ホロコースト」と呼びならわされていることには注目しても良いだろう。つまり、この歴史的な大規模弾圧/殺戮を「燔祭の供物」と捉えようとする考え方があるということだ。