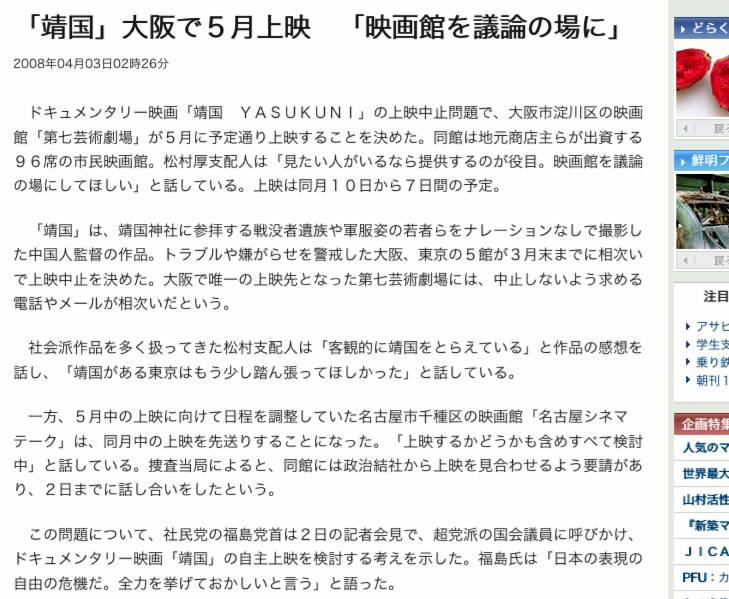怒鳴り合う「思想」:映画『実録・連合赤軍』に殴られる
Monday, April 21st, 2008
「映画」と言えばテレビでプレビューを流しているようなハリウッド系映画や、次から次へと作られるテレビのホームドラマみたいな邦画作品くらいしか知らないという方はお読み下さらなくていい。
■ テアトル新宿
実録・連合赤軍 あさま山荘への道程
5/10(土)よりモーニング上映決定
タイムテーブル
〜5/9(金) 11:30/15:20/19:10〜22:40
5/10(土)〜5/23(金) 11:00〜14:30 ◎1日1回上映【第58回ベルリン国際映画祭】(2008年)
《フォーラム部門》招待作品
★祝【第58回ベルリン国際映画祭】2冠受賞!!★
●最優秀アジア映画賞(NETPAC賞)受賞!
●国際芸術映画評論連盟賞(CICAE賞)受賞!
★【第20回東京国際映画祭】★
●《日本映画・ある視点》作品賞受賞!
映画から受けるダメージはゆっくりとだが確実に作用している。
彼らを「狂信的」とは呼びたくない。こうした「正しさ」への信頼の感覚とは、われわれが若い時に一度は通り抜けてきたものだからだ。私の近代主義や高度技術文明に対する批判というのも、その根っこは高校生くらいの頃に初めて出会った哲学に求められるのだし、「間違いつつある文明」に対する警鐘として殉じたいという気持ちとともにあったものだ。
だが、機関銃のように指導者の口から発せられるきわめて抽象的で観念的な言葉、言葉、言葉。時間を掛けて考えれば、「純粋な思想」として理解できなくはない理論でも、現実との折り合いを付けられない、こころの表面を上滑りするばかりの怒鳴り声が、ひとの耳を仮借なく襲う。崇高なはずの「思想」は、すべて怒鳴り合いの中で応酬される。あるのは、対話ではない。今でも平壌(ピョンヤン)からのテレビ放送で見ることのできるようなアナウンサーによる演説調のアジであり、背筋に力が篭って堅くなった人間の発する黒い声音によって撃ち出される単語の矢である。
この「熱さ」はあたかも幕末の志士たちが登場するドラマや映画などでも描かれてきた、相互に斬ったり斬られたりする若者の群像ではあるのかもしれないが、青春を描いた映像だとは言いたくない。その上滑りする抽象的な言語に限っては、ただ暴力的に繰り返されるばかりで、ほかの若者を真に考えさせ、理解させることができない。
現に、「まったくわかっていない」と指導者に怒鳴られる若者たちを、本当に分からせることのできる、実感と現実感を伴った言葉と経験を、指導者を含め、誰もが持たない。(その指導者だって指導される側とほんの数年の歳の差しかない。)
したがって、こうした純粋な思想的な展開について行くことのできる極一部の(理屈っぽい)人間だけが、かろうじて「わかっている」のであり、「指導的立場」に居座ることができる。そして、「わかってしまった者」は、自分のこれまでの「間違い」を認めないわけにはいかず、認めて自己を批判し自己否定する者は、負けを認めて「思想的」にも指導者に従わざるを得ない。「間違った者」は、それを諒解すれば「正しい者」に従うのが思想的に「正」となる。かくして支配と被支配、指導と被指導が、思想という純粋観念の力を得て実現されるのである。
一方、「わからない者」は、どこまで行ってもわからない自分についての「総括」だけを求められる。思想をわからない者が「自己を総括する」などということは撞着以外の何ものでもない。そのようなことは理屈上不可能なのだから、わからない者に総括を求めることは、教育に失敗した教師がわからない生徒に反省を促しているようなもので、まったくもって理屈に合わないのであるが、指導者の絶対的立場は、そうした自分に向かう批判だけは狡猾に封じる「へ理屈」を持っているのだ。このようにして「総括」の意味は次第に失われて行く。総括を求める指導者たちは、「自分で答えを出すのが総括だろ」という理屈によって、真の指導や教化の責から免じられてしまう。
どこまでも「わからない」メンバーには、言葉による執拗な批判と人格の否定、そして、間もなく、生命を滅ぼす身体的な暴力が待っているのである。これは、北朝鮮の強制収容所やカンボディアの「キリングフィールド」、文化大革命時代の中国、そして戦前・戦中に憲兵が大威張りで闊歩し、隣組が相互監視をしていた日本、などなどに起きたことではないのだ。これは70年代に、われわれが日常を生活していた隣で起きていたことなのだ。
「正しい者」が怖い。この感覚は、自分の中では長いこと封じ込めて来たものだ。正しい者を怖がってはイケナイ。正しければ正しいほど、それは克服され乗り越えられなければならないから、ということもある。だが、このバランス感覚によって「正しい者」が自分に近づいて来たら逃げたり避けたりしないで、可能な限りその「正しさ」を問うという姿勢に自分を向かわせたのである。健全な相対化を旨とする人間にとって、したがって「正しい者」を怖がらずに、近づいていって検討してみるというのは、方針としてむしろ必要なことであった。
だが、ある集団の閉塞的な状況において、「正しさの感覚」の飛び抜けた者は、カリスマになる可能性があり、それの正否を問う存在(批判者)がいなかったり、批判者を封じ込めたりすることに成功すると、その閉鎖世界の中で「まったき暴君」となる。自分に正義があるというその恐るべき感覚。それは若くて純粋な時期の若者にこそ起きがちなことではあろう。40の訳の分かったような中年よりも子供の残酷さに近いものを彼らは持っている。特に、異なる世代がおらず、したがってさらに上のレベルから批判できる存在がなければ、「革命の理想」というものは、暴力的手法を得て、現実のものとなり得る。成功した革命とは、案外こうしたものかもしれない。
「正しい者」の行為の総ては、達成されるべき理想や目的のための手段となり、いかなる手段も正当化できるという思想に到達し、すべての特権と絶対的な権力を手に入れる。それがたったの30〜40人足らずの若者の集まりであったとしても、その絶対的権力に逆らうことはできないという空気が醸成され、それに対抗する勇気を失えば、殺人やリンチでさえも「理想へと近づくための方法」となり得るのだ。これは倫理的な社会(理想)を実現させるために倫理を踏みにじっている自己の立場を容易に忘却する。
自己批判と総括とを迫られ、呵責なき暴力を振るわれ、「こんなこと、意味あるのか? それが革命なのか?」と断末魔の中で叫ぶ男たちは、完全に秘境の地で世間から隔絶された「軍事訓練」のキャンプの中で、口を封じられ、まさにその素朴な疑問ゆえに、集団リンチを受け、死んで行った。ほんのちょっとした指導部への疑問でさえも、すべて「革命的でない」「自己の共産主義化が足りない」などの理由で圧殺される。かくして少人数のキャンプが恐怖政治となる。理想に燃えた若い青年たちの夢が、かくも脆く修羅場と化す恐ろしさ。この恐ろしさは楽しめる怖さではない。彼らの純粋な「正しさの感覚」ゆえに、そして勇気を奮えないために許される「狭い世界での専制政治」ゆえに、まことに後味が悪い。だが、この後味の悪さから逃れようとしても、描かれているものが虚構ではなく、われわれが生きていたこの世界において、現実の物語として起きていたのだという事実性から、われわれは逃れることができない。
確かにこの映画は、左翼活動家の愚かさを広く伝えるための手段として用いられてもおかしくないが、国を想う右派活動家によっても同じことは起こりうるし、起こされてきたことだ。「正しさの感覚」への無批判な信頼と、声を上げるべき時に上げないわれわれの「勇気のなさ」が揃えば、いつでも、何度でも、この地上に「実現してしまう」可能性を持つ出来事なのである。悲しいことだが、これが「人間性」なのである。