「Sim 駅前留学」で遊べ
Sunday, October 28th, 2007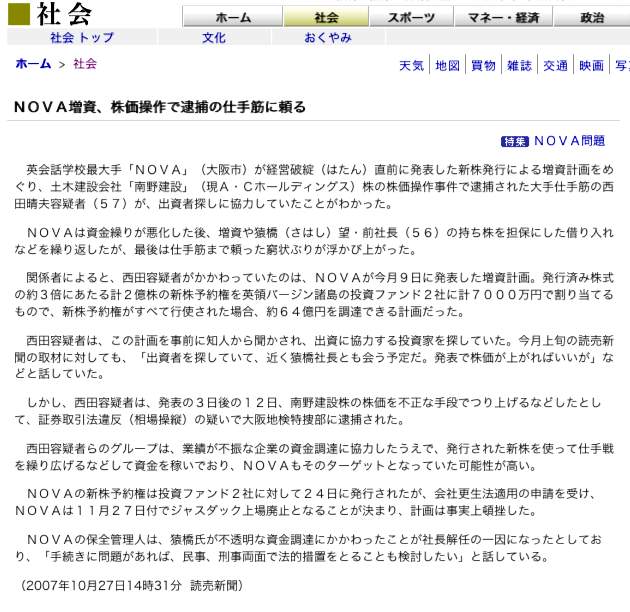
■NOVA増資、株価操作で逮捕の仕手筋に頼る(読売新聞 - 10月27日 14:42)
英会話ビジネスで破綻の憂き目を観た会社はNOVAが最初ではないと記憶する。ラド、ABC、NCB、などなど。だが、考えてみれば、町の弱小な英会話学校はともかくとして、「成長する英会話学校」なるものは、すべて倒産の危険を孕んでいると考えるべきではないのか? だって、「成長」しているんだよ。成長すれば、無限大に成長はできないんだから、どこかで何かが起こる。
英会話教室というものは、そもそもその本性からして、合理化が難しい分野だ。生徒何人かに対して、必ずひとりの先生が必要で、少数の先生で一気にたくさんの生徒を教えるというようなマス授業でも開発しない限り、合理化は難しい。だがそれは少数で丁寧に教えますという方針にも矛盾し、そもそも採用できない方向性だ。ということはどういう事かと言えば、生徒を沢山抱えるなら先生も沢山抱えなければならず、企業として規模を大きくするということ自体が、人件費の比例的な増強なしには行えない。「一発当てる系」のビジネスとは、一度これというような「金型」を作って、それによってできる製品が一発当てたら、その金型を使ってパカパカとたい焼きを焼くように短期間にどんどん量産できるようなものでもない限りそもそも無理なのだ。つまり、ソフトの開発とそのソフトの量産というのがひとつの条件だ。無人化を進めることのできる過程を含む製造業、一部の出版業、そして極々一部のメジャー音楽産業にはそうした「一発当てる」可能性がある。だが、教育産業が一発当てて成長するというようなことは、その教育という無人化の採用がそもそも構造的に不可能なビジネスにはあり得ないのだ。これはちょっと考えれば分かることだが、仕事というものを理解する基本だ。英会話学校のようなものは、ひとつひとつ手作りをしていくしかないデザイン工房の様なものだ。
だがどうしてNOVAのような「急成長」という異常事態がこの産業の中で時折起こるのか、それを考えるのが重要である。一言で言ってしまえば、イメージ戦略が「一発当たる」というケースだ。どれだけ資金をつぎ込んだか分からないが、ピンクのNOVAうさぎを使った同社がテレビCMその他のメディアを通して相当に露出されたことは誰もが知るところだろう。人々はそのイメージで企業が大きくて先端的で頼りになるだろうことを刷り込まれる。広告代理店はこうしたイメージ戦略を打ち立てて、払われたお金に応じて企業を有名にする。だが、イメージがダウンしてきた時の現状維持のためのお手伝いまでは面倒を見ない。イメージが悪くなったのは企業の「自己責任」だから失敗は企業の責任だ、というわけだ。
したがって、一気に成長してあちこちに支店を開くような「英会話学校」は、突然資金繰りが悪くなって「倒産」というようなリスクをすべて持っていると考えるべきだ。これは単にNOVAの社長や経営者に問題があった(あっただろうけど)というようなだけの話ではない。イメージ戦略という幻想によってそれを支持し、ダメと分かったらさっさと撤収しようとする、利用者、教師、出資者、のすべての合作なのだ。株式市場と似た様なものだ。
昔、「Sim City」という秀逸な都市計画ソフトがあったが、ぜひ「Sim 駅前留学」というのを出して欲しい。成長する英会話学校の教室をどれだけの間、駅前の一等地に建て続けることができるかというモノポリーを競うゲームだ。駅の数や習いたい生徒数はだいたい決まっているので、ある程度まで成長したら必ず破綻の兆しが見え始め、大体早晩には倒産する。
駅前に一つ学校を建てるところから始める。日本に遊びにきている外国人を安く雇い、プログラムを決め、価格を設定し、人気が出れば別の学校を建てる。イメージ戦略が必要なら広告代理店に幾ばくかの資金を投入する。一気に生徒数が増えるので、人員と学校を増やさなければならない。さまざまな付加価値的なプログラムを開発して、遠隔地教育にまで手を出す。長くゲームをやればやるほど、どんどん難しくなってきて倒産回避は困難になる。それをどうにかしてやりくりをして、一日でも長く経営し続けることができれば勝ち、というシミュレーションゲームだ。
それほどかように、「成長する学校」の経営は難しいということをこのゲームはわれわれに実感させてくれるだろう。なにしろ、スポーツジムみたいにお金を払っただけで来なくなる生徒数まで計算に入れて適正な教室数を考えているのに、倒産するとなると、来なかった生徒までワラワラと全員戻ってきて払い戻しを請求するんだから怖いよな。
[話は変わるが、姓名判断的にもNOVAは拙いよな。No VAだよ。VAに「No」と言ってはいけない。逆さにしてAVONはどうだろう? え? そういう名前の会社がある?]





