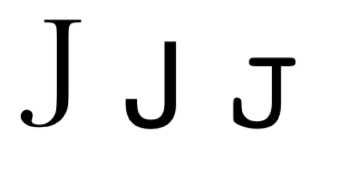Jの陰謀
〜 新しいアルファベットを巡る仮説的表象論 [3]
Tuesday, February 27th, 2007


図版引用先:CELADON CUPCAKE
■ クリスマス装飾の象徴性
クリスマスに欠かせない装飾の中にはこれまでに見て来たようにリース wreath やクリスマスツリーなどには、色や形、そして構成要素やその数といったものの中に、記憶に残る特徴として無視すべきでないエッセンスがある。あるいはツリーに付随するものとしては、その頂点に掲げられる輝ける星、そして吊り下げられるさまざまな光輝を発する球体(花火の弾のようでもある)というものがある。中でも伝統的にクリスマスに付き物の象徴的アイテムのひとつとしてJ字型のキャンディー・ケイン candy cane(杖型キャンディ)のことを忘れるわけにはいかない。それはクリスマスケーキに付けられることもあれば、リースに絡められることもあり、またツリーに下げられることも多々ある。ポストカードのようなものには単独でキャンディーと思われるデザインがあしらわれることもある。このシンボルはクリスマス期間中、商業主義によっても広く採用され、またはそれに積極的に便乗し、ほとんどあらゆる場所と言って良いほどさまざまな場に現れるものである。


図版引用先:
Children’s Cross Stitch Winney the Pooh
NorthlandSent Wreath Company
クリスマスツリーがそもそも何を表すものなのかという基本に戻れば様々なことが憶測できるが、ひとつの重要な解釈には「世界樹」としてのクリスマスツリーと、その枝に撓わに実る《収穫物》という考えがある。クリスマスツリーが世界の中心を表す世界軸(axis mundi)であり、それが一年という季節の周回の閉じる時、すなわち冬至の祭りの時期に登場するということ、そしてその木に稔るさまざまなオブジェは、その垂直に屹立した男性原理としての神的/父権的「リンガ」が子としての人類へさまざまな「実り」をもたらしたことに由来する。

図版引用先:Button & Needlework Boutique
クリスマスの時期にプレゼント交換をするという現代の世俗的な慣習も、その文脈で捉え直せば、まったく意味がないこととばかりとは言い切れない。つまりわれわれにとってクリスマスのプレゼントが「メイシーズ*の陰謀」のためだという説明だけで満足できる話ではなく、むしろ商業キャンペーンが始められた時代よりずっと旧い伝統を持つ贈り物の慣習に、商業主義が便乗してグローバル化したものと言うべきであろう。現に、アメリカの百貨店の影響下になかった旧ソ連においても──すなわち一見、脱宗教化されていた時期のソ連においても──この冬の時期にこうした贈り物の交換が行なわれていたことは事実でなのである。これは近年のクリスマスの祝祭的お祭り騒ぎが商業主義のせいだけでは説明できないことを証している。
* Macy’s: アメリカ合州国の有名百貨店。
さて、そのクリスマスツリーの枝に「実っている」さまざまな象徴物のひとつが、J字型のオブジェであることを、われわれはここで改めて捉え直すことができる。それは装飾品がある種の「供儀物」であるという捉え方である。われわれはこうして聖書における様々な鍵を担う登場人物達(特に男性)の名前のイニシャルが英語において、ステッキ状のJに置き換えられていることの意味(理由)に近づくことができるはずである。


図版引用先:
Elegant Stitch
“Christmas clangers” @IntakeHigh
もうひとつ思い出されるヒントは、クリスマスイブの夜に子供達がサンタクロースからの贈り物を期待して用意するあの象徴物である。それはしばしば暖炉の近くの壁(マントルピース)に取り付けられ、この中には翌朝、食べきれないほどのキャンディー、あるいはクリスマス・プレゼントなどが詰められているであろう。これはクリスマス・ソックス Christmas Stocking である。この袋状のものに詰められる豊穣の収穫物という範型は、コニュコピア*という豊穣のホラ貝の象徴物と明らかに類型のものである。こうした角笛状の貝には当然のことながら男性原理(陽物)的な暗示があるが、そもそも住居の煙突とは家庭というもうひとつのミクロコスモスにおける世界軸であり、男性原理の象徴としても存在する。そこでクリスマス・イブの夜に子供達に与えられる贈り物の習慣を思い出せば、この靴下が象徴的な煙突の足もとに溢れ出しこぼれ落ちる「供儀物」の分配の一種と捉えることができる。
そして、多義的に解釈可能だが、その靴下がわれわれに注意を向けるよう指し示すものは、容れ物の形状である。それは《J字型の容れ物》であり、キャンディー・ケインと同様に、靴下や飴という物品の持つ機能的属性よりも、その形状的属性こそに表徴的本質があるのである。

図版引用先:Gary Elliott @FOUNTAINHEAD, College of Technology
記号でありながら、それ自体が具体的な物品であることから、それが比喩であることが了解しにくい。それが、何かを指し示すものであり、指し示される対象が別に存在することが一見すると分からないのである。
記号としての共通点は、“J”で表されるものがクリスマスツリーにしてもソックスの中の菓子にしても「味わわれるもの」であること、そしてそれこそが神への供儀物であり、子供達に与えられる供儀物の分け前なのであることをわれわれは再び思い出すであろう。
* Cornucopia: “Harvest Cone”とも“Horn of Plenty”とも呼ばれる。ギリシア神話における逸話より。山羊の乳で育ててくれたことへの返礼として、ゼウス Zeus が乳母(育ての親)アマルテア Amalthea に山羊の角を贈ったと言われるところから。溢れ出る収穫物が特徴である。
■ 祖型的「自己犠牲」の象徴としての“J”
われわれがもはや記憶から消し去ることのできないほど深いトラウマとして、そして最も広く知られた“J”の象徴の王様は、イエス・キリスト Jesus Christ である。もともとがヘブライ名であったその名前の表記が最初から“J”とされたわけではないことはすでに知られたことである*が、それがやがて欧州のほとんどの地域で“J”をイニシャルに持つ表記となり、ついには固定化された。
これは先述したようにある意味異常とも言いうる事態であるが、それが定着した後なら、「人の子・イエスの誕生日」ということに通例なっているクリスマスの期間の象徴に、“J”形状の記号がかくも多く見出されることは、ある程度は自然であるとも言える。したがって、通説にもあるように「キャンディー・ケインの形状は、Jesus Christの“J”である」と言えるわけである。そしてまた、その救世主イエスを表象する道具である「羊飼いの杖」の形状でもある、とも言えるのである。こうした説明は一般的にすでに受け入れられているか、あるいは改めて説明されれば多くのクリスチャンが抵抗なく「なるほど」と納得できる俗説であるとここではしておこう。

図版引用先:The History of the Candy Cane
だが「杖」と救世主のつながりは、イエスの生涯を描いた子供向けの「聖書物語」の挿絵やクリスマスカードにおいて示されている図版の存在という事実にあるのではなく、むしろ「先端の曲がった杖 cane」が、自己犠牲を通しての救済を象徴してきたことにある。「先端の曲がった杖 cane」が、《ペリカン図像》にも見られるようなある象徴機能の範型を共有していることにこそ、より重要なつながりが見出されるのだ。
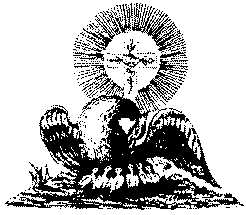

画像引用先:
Birds in Alchemy @ CRYSTALINKS
Distillation Equipment @ CRUCIBLE CATALOG
錬金術図画にも登場するペリカン図像は、キリスト教の伝統の中でも採用されており、自らの血を購いの血として胸から地上に放出するキリストの象徴である「神の子羊 Agnus Dei, Lamb of God」と同様に、自らの血を子に与える親ペリカンの像として現れるものである。その形状的特徴は図版からも分かるように、「長い首を内側に曲げ、嘴(くちばし)を自らの胸に突き立てる」構図なのであり、その形状のエッセンスを抽出すると、「曲げられた長い棒」ということになる。
つまり杖は、当時三十代前半の若さであったと憶測されるイエスが使用するものとして最も相応しいものであると考えるよりは、「曲げられた長い棒」が、「我が身に嘴を突き立てる」自己犠牲的行為を通しての救済を意味する記号として機能することにある。
ペリカン図像が錬金術の象徴体系等に見られる様な多層的な意味を持つことについてはここでは深入りしない。秘教的象徴を保持する図像群の中で、とりわけ「購いの血を流すペリカン」が、「Jの祖型」のグループに属しており、そのヴァリアントがペイズリーのパターン paisley motif* の中に見出されるようになることだけをここでは断っておこう。


[ここにペイズリーの画像を持ってくる]
図版引用先:
The Pelican (by Wor. H. Meij) @ Let there be light! (Welcome to the place for Masonic knowledge!)
Agnus Dei @ Wikipedia
* スコットランドのペイズリーで量産されポピュラーになった装飾紋様であったためにこのように呼ばれるようになったようだが、そのオリジンはどうやらインド(カシミア/カシミール)に求められるようである。
Secret Gardens: “Paisley” Motifs From Kashmir to Europe @ Museum of Fine Arts, Boston(http://www.mfa.org/exhibitions/sub.asp?key=15&subkey=617)
Paisley pattern stretches across millennia @ Hindu Widsom(http://www.hinduwisdom.info/Hindu_Culture2.htm)
だがより深い問題は次節で観ていくように、救世主イエスばかりでなく、“裏切り者”**ユダ Judas、洗礼者ヨハネ、福音書家/十二使徒ヨハネ John、そしてヤコブ Jacob やヨゼフ Joseph など、聖書世界のメジャープレイヤーの多くが、同じく“J”の記号を以てその世界を絢爛に飾っているという真の理由の方である。そして(ヨゼフを除いては)その登場人物の幾人かが、《殉教》によってその生涯を終えていることにわれわれは注意を喚起すべきである(洗礼者ヨハネ、使徒ヨハネ、使徒ユダ、使徒ヤコブ)。殉教とは自らが燔祭の羊となることであり、神への供儀物となることである。真偽の評価はともかくとして、それが「救済」へと結びつくと信じられたのである。
* What’s in a name? (By Brian Felland)
ヘブライ語のスペルから考えれば、”Yahuah”か”Yahshuah”であるべき「人の子・イエス」のスペルが、どのような事情で“Jesusとなり得たのかの経緯について言及している。
** 飽くまでも現正統派が編纂し、今日「原典」として知られている新約聖書による解釈。もはやユダが裏切り者であったかどうかについては疑問の余地があるためだが、ここでは深入りしない。