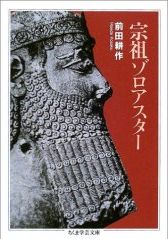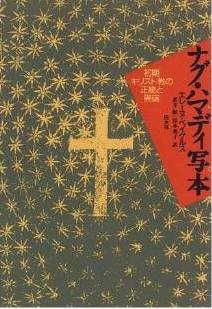■ 随時更新中 ■
p. 39
ユダヤ教の終末論では、宇宙論的な観点と歴史的な観点とが結合されている。宇宙論的な観点が優勢であることは、終末が真に世界とその歴史との終りであるということで明らかである。このような歴史の終りは、もはや歴史そのものには属さない。したがって、歴史が一歩一歩目指して進んでいくところの歴史の目標とは言えない。終りは歴史の完成ではなくて、歴史の終止である。それはいわばこの世界が年をとって死ぬということなのである[『第四エズラ書』5・55、シリア語『バルク書』85・10、『第四エズラ書』4・48〜50参照]。
この辺りについては、例えばエリアーデの著作を読んでいても気を付けなければならないと幾度となく思った部分である。「世界の終わり」に相当するフレーズに訳文では「宇宙的な更新」という言い回し(おそらく英語や仏語では“universal”, “universe”に当たる単語が使われている)が頻繁に出てくるが、それは太陽系や銀河系を含むような所謂天文領域の「宇宙: space」ではなく、われわれの暮らす“cosmos”としての「宇宙」のことと捉えなければ議論上の意味がないのは当然だと感じられたからだ。「終末論」の議論においてわれわれに関わりのあるのは、ブルトマンが言うように、歴史的な(こう言って良ければ人類史的な)観点であって、人文学的な興味である。「天文学レベルでの宇宙的な終末」など、われわれにとっては考える意味がない(便宜的にだが)。むろん「窮極的な宇宙の終わり」についてまったく興味がないといえば嘘になろうが、それはどちらかと言えば単なる「好奇心」「科学的興味」の問題なのである。だがどちらかと言えば「終末論」は、われわれにとっての「死」、とりわけ「集合的な死」が問題になる。というか、われわれに関わることだからこそ、議論される価値がある。つまりそれはこれまで人為的に人の思惟と工夫によって作り上げてきたコスモス、すなわち「秩序」や「文化」そして他ならぬ「歴史」を築き上げ相続してきた「人類の滅亡」のことが終末論の核なのである。
p. 39
新しい創造が古い世界にとって代わるであろう。しかも、それら二つの世の間には何らの連続がないのである。過去の記憶そのものは消失し、それと共に歴史が消失するのである。新しい世では空しいものは過ぎ去り、時も年も無に帰し、月も日も時間ももはや存在しなくなるであろう[『第四エズラ書』7・31、スラヴ語『エノク書』65・7以下参照]。
これが「周回する世界」に関する問題共有を難しくしている第一の理由である。その二つの世の間には、巨大な「Ω形状」の祖型的図像群によって暗示される以外にないような、或る「出来事」があったからである。だが、ブルトマンの主張は完全に正確とは言い切れない部分もある。実質的に「二つの世界の断絶」は起きたが、連続が完全にないとは実のところ言い切れないからである。
それは「かつての世界」の存在に言及する神話の存在、象徴図像の存在、黙示録的文学の存在、あるいは「世界の七不思議」と言われるようなわれわれの常識で説明できないような事物 (Oparts: Out-of-place Artifacts) の存在、そしてそもそも「われわれ自身の生存」によって証明されている生命的な連続である。本当にその「断絶」によって「世界が完膚なきまでに一旦終わった」のだとすれば、われわれ自身がこの世界に存在していないことになる。ここ数千年の内にわれわれが無から生じたのでない以上、歴史と歴史の間に存する至福の(もとい、「過酷な」)時間を生き延びる少数の人間がいたということなのである。したがってこの「生物上のサバイバル」により、神話や象徴の存在も同時に説明される。
p. 55
洗礼を受けた信者は「キリストに」(in Christ)ある。それ故に、「だれでもキリストにあるならば、その人は新しく造られたものである」(『コリント人への第二の手紙』5・17)、「古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである」(同所)ということは真である。新しい世(The New Aeon)は既に現実である。というのは、「時の満ちるに及んで、神は御子をつかわされた」(『ガラテヤ人への手紙』4・4)からである。イザヤによって約束された至福の時が現在ここに来ているのである──「見よ、今は恵みの時、見よ、今は救の日である」(『コリント人への第二の手紙』6・2)。ユダヤ人が終りの時に来るものとして待ち望んだ霊の賜物が、今信者にあたえられた。それであるから、彼らはすでに今「神の子らであり、僕(しもべ)である代わりに自由な人間である」(『ガラテヤ人への手紙』4・6以下)。
これほどかようにキリストやキリスト教の本質を言い表す聖書からの引用の収集というのもなかなかお目に掛かれない。これを読んで自分が考えたのはそれを解説することではない。この言葉に別の言葉を代入すると言う、いつものあれである。私風には以下のように置き換えられるだろう。
文明の恩恵を一度でも受けた信者は「文明と共に」(with and within our Civilization) ある。それ故に、「だれでも文明と共にあるならば、その人は新しく造られたものである」、「かつての古い文明は過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである」ということは真である。新しい時代(The New Aeon)は既に現実である。というのは、「時の満ちるに及んで、神は文明を地上にもたらした」からである。預言者によって約束された文明最大の隆盛期(すなわち至福の時)が、今まさにここに来ているのである──「見よ、今は恵みの時、見よ、今は技術による救済と福祉の日である」。かつての人類が終りの時に来るものとして待ち望んだ「霊の賜物」と呼ばれる「文明最大の恩寵」あるいは「世界至上権」が、今、科学技術に与っている文明の支配者にあたえられた。それであるから、彼らは実質的に、今「神の子らとなった。奴隷であることをやめ、自由な人間として振る舞うであろう」。
こうしてみれば、「キリスト」というものが何を置き換えるものなのか理解することが容易である。信者であるか否かに関わりなく、われわれはその「恩恵」を受けているほど、その影響力は大きい。あるいは反対に、その「害」を被らないでいることもできないのである。そしてキリストを「置き換えるもの」を無条件に「善なるもの」と信じられる人々がその信者であるということができる。そしてまた、このキリストによって置き換えられる「何か」が最終的に何を人類の上にもたらすのか、そしてそれは何故また「戻って来なければならない」のか、そのすべてを一気に了解するであろう。
p. 190
ギリシャの科学と哲学との根底には人間の自己了解* (self-understanding)が横たわっており、それはまたそれで科学によって形作られているのである。ギリシャの悲劇では、特にエウリピデスによって、この自己了解が問題とされた。そして、それは結局、いずれにしても民衆の大部分にとっては、グノーシス主義** (Gnosticism)において崩壊した。グノーシス主義との関連において、と同時にこれに反対してキリスト教が現れた。
* 訳本では「自己-了解」とふたつの単語の間にハイフンが入れてある。英語表記の“self-understanding”に併せたものであろう。
** 訳本では「ノスティシズム」と英語的に表記されていた。現在ではもっと親しみやすくなった「グノーシス思想」という訳語に置き換えている。
この記述から伺い知れるのは、科学の伝統は(当たり前だが)、ルネサンスを経て人間回復の兆しが出てきて以来のことだとか、ローマ・カトリックがプロテスタントに徐々に圧倒されてきた頃、すなわち実証主義科学が日の目を見始める比較的最近(16-17世紀頃)に発生したというのではなく、キリスト教成立以前に遡れるだけの、古いひとつの潮流としてすでにあったことを明記しようとする意図だ。ブルトマンによれば、むしろ、キリスト教はそうしたある種の「知識」に対する警戒と反動とによって産み出されたことになる。これは新しい考えでもなんでもないが、キリスト教を捉えようとする時の一つの可能な立脚点を提供する。そして、それはきわめてありありと想像することのできる状況である。
また自己認識(本書によれば「自己-了解」)と呼ばれる自己への意識の芽生えが科学志向という方向を産み出すとブルトマンは言っているのである。ただし、そうした厳しい自己認識を基盤とする科学と哲学というものは、ギリシアにおいてさえ、一握りのエリートたちによって独占されているものに過ぎず、大半の者たちにとっては、無意味であったか、あるいは自己崩壊をもたらす有害なものでしかなかった。そこで当時「大多数」にとっての救済が、別途、課題となったのであろう。人はいつでも何らかのテーマなしには生きて来れなかったのかもしれない。
ところで、歴史的に概括したときのユダヤ=キリスト教(ローマ・カトリック)というものの機能とは何か? それはひと言で言うなら、「反知」ということに尽きる。とりわけ、文明を象徴する本体である「キリスト」に降り掛かる受難を教え伝える伝道師たちの役割とは、「それ」がやってくることの福音(ニュース)と「それ」がやがて殺害されることの予定と、その死後、「それ」がまた再び戻ってくることの予知を行ない、その象徴的に言い表される「人間の文明の持つ福音と危険」を普く伝えることである。
「知」が人類によって取り扱えないほどの危険性を孕み、それが広く人類の共有財となることによって引き起されるであろう、かつての人類に起こったのと同じ陥穽に走り至らないようにするための制動装置(ブレーキ)として機能しようとしたものと捉えることができる。とりわけカトリックの「知」(科学的知 ≒ 異端思想)に対する弾圧があれほど苛烈を極めたというのも、単に「人間の組織」としてのキリスト教会の安定的持続と権威維持のためばかりではなかった(もちろんそれが重大な関心事であったことは疑いがないが)。
それは全人類規模の「滅亡」を少しでも先送りし、人間の知への欲求を棚上げするための実力行使でもあった。それは実際問題、ルネサンス(ヒューマニズムの復興)が起き、科学技術が目覚め、聖書が印刷され(封印が解かれ)、それらが人々に広く共有され、カトリックという絶対的存在に関してのプロテスタンティズムによる相対化が徹底するまで、かろうじて機能した。事実上、聖書を原典とする宗教が、その原典共有を永らく嫌っていたと考えられるのだ。いずれにしても、この制動装置(ブレーキ)としての「教会」の権威は、キリスト教成立時代の黎明期から、異端審問委員が発足されいよいよイエズス会の暴力的な振る舞いが世界の各所において目に余るほどになる16世紀まで、ほぼ「千年以上に渡る期間」、欧州を支配したのである。
本来、ブレーキとして働くべき「教会」が、自らの放逸と堕落、富の偏在、その他枚挙するにも厭わしいようなあらゆる「人間の組織」によるいかにも人間的な失敗の数々を引き起し、その果てにプロテスタンティズムの勃興を許した。それによって、「教会」は人間性と個人主義を中心に据え、そのアクティヴィティを讃えて止まない加速装置(アクセル)として、すなわち「近代資本主義の精神」の基盤を提供するまでになる。まさに見事なまでの転向振りである(もちろん、カトリックとプロテスタントという別の組織を同じ「教会」という言葉で意識的に混同させた言説であることは承知の話だ)。
だが、如何に彼らが完璧からほど遠い存在だったとしても、本来教会は「科学が宗教を凌駕させないため」のあらゆる試みであり、その役割にはまさに「反知」すなわち「アンチ・グノーシス主義」とでも言い表されるような終止一環した働きを持っていた。ルネサンス文化の側(ヒューマニズムの立ち場)から言えば、「暗黒時代」と形容されるヨーロッパ中世は、まさにカトリックによって形作られたコスモス(秩序)の世界だった訳である。それは自覚的な意図を持った「反近代主義運動」だった。
だが、あらゆる人類の行為はそれによって成し遂げようという目的をもたらさない。意図がその反対の結果をもたらすという逆説は古今東西に見られるのである。歴史を読むということは、いかに意図が目的から逸脱するのか、それが何故起きるのかというのを考える行為なのである。
(more…)