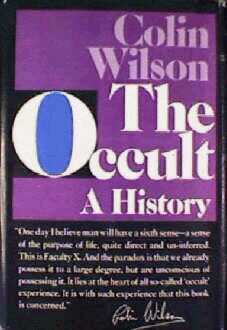真性《オカルト》論について
あるいは「日本語において言葉の倒錯への傾斜は余りにも急だ」
あるネット上のコミュニティで、「スピリチュアル」という言葉の濫用によって、その言葉を使うことが躊躇われるような状況に今の日本はなっているという嘆きの言葉が載っていた。その正統な指摘はそのコミュニティでなくてもそのように感じている人が多いのではないかと思われるほど、否定しようのない活況を呈しているのは実際本当であろう。
そこでの発言のいくつかをそのまま引用してみる。
人間性にとって最重要なトピックである”精神”の問題が、多くの日本人にとって、オカルトの文脈で語られてしまっている、ということなのだから。
もうひとつある。
例えば、「オウム」の仏教の本来的意味は、「永遠」です。しかし、いまやこの言葉は死んでしまいましたね。あーこのままでは「スピリチュアル」が「オカルト」になってしまう・・・
「スピリチュアル」という言葉が本来の意味で使いにくくなってしまったことを嘆くこの二つの意見は、「オカルト」が怪しげな精神主義やカルト宗教絡みのものであるというような、あきらかに否定的意味で使われている典型的事例とも言うことができる。だが、そもそも「オカルト」という言葉にそのようなニュアンスはあったのだろうか? 私の考えでは、それは単に「隠された秘教的伝統(神秘主義)」のことに過ぎず、それ以上でも以下でもない。むしろ「隠された」という意味内容が、長い時間の経過の過程で別のものに置き換わってしまったことを端的に表す例のひとつであるように思えるのである。
このことは現代人によってはなかなか理解しにくいことであろうが、「Occult オカルト」が、きわめて暗い内容を含む対象を指すものであるにしても、その研究自体はそうした否定的な意味を持たず、ある正当な理由で、むしろ正面切って論じるべき価値のある真剣なサブジェクトであった。その意味においては、1630年頃の欧州で、“あーこのままでは「オカルト」が「似非神秘主義」になってしまう・・・ ”と嘆きたくなるような事態があったと言えるのである。つまり、目下「スピリチュアル」という言葉の濫用によって起こりつつある迷惑事態は、遠い昔に「オカルト」という言葉にも起こっているのである。
今日では真面目に「オカルト」を論じようと思っても、論敵を揶揄して使う際の「オカルト」というニュアンスの方が今では勝ってしまっており、そうした怪しげな似非神秘主義(目に見えざるもの全てを含む似非科学など)などの否定的意味以外の本質を伝達する力を失っている*のである。その点では、こうした本質的意味の回復を図ろうという論理は、それが如何に正しかろうと、おそらくほとんど現実的な効力を失ったことを認めざるを得ない状況にあるわけである。
* このような事態になった理由には、70年代にブームになった「オカルト映画」というジャンルの登場もあるだろう。『エクソシスト』や『オーメン』、そして『キャリー』といった悪魔払いや黙示録的預言の実現、あるいはサイコパスによる猟奇事件といったテーマが大々的に映画の題材として扱われ、それらが十把一絡げに「オカルト」の名前で呼ばれたことが大きいと思われる。今上げた映画はどれも同じようなテーマを扱っておらず厳密には何の共通点もない。
だがそれでもあらためて、「オカルト」の持っていた失われた《本義》に戻った時、その言葉は「心によって把握できず、人知を超えたもの」という1545年頃の本来の定義説明によって意図されたような、「隠された真実」「隠し伝えられた秘儀」「隠された秘教的伝統」の意味に限定して使われるべきなのである。それは、そうした学問/研究領域を端的に表す言葉がそれ以外に存在しないから、とも言えるのである。無駄なことであるかもしれないが、オカルト研究家の立場としてはそのように言いたいところなのである。
あらためて「隠された」という言葉の意味内容を考えてみよう。それは「visibleな肉体的/物理的事象」に対する「invisibleな精神的/心理的事象」というような意味で、「目に見えない」ことを扱うのではなく、ひとつにはその問題の現実性を論じるための証拠が「遥かに古い時代に失われている」という意味で「隠された」と表現する以外にないような《何か》を指す言葉なのであり、別にスピリチュアルの意味でも精神性の意味でもないのである。あえて誤解を恐れずに記すなら、どちらかと言えば、真性の《オカルト》はどこまで行っても物理的事象なのであり、また可視の問題を扱うものでしかない。それが現実的には不可視であるのは、単にそれが人知を超えた現象であり、また大変昔*に起きた現象であるという意味ででしかないのである。
* 「大変昔」とは言っても人類が地上に現れて以降の話なので、地質学的なスケールの時間領域を扱う訳ではない。あくまでもわれわれの知っている文明を築く傾向のある人類の登場以降の最近の話であるとも言える。
そしてそれが「隠された」と言われるもうひとつの理由は、その内容の重篤性によって無かったことにされた――すなわち文字通り「隠された」――ものであることを忘れるわけにはいかない。つまり「歴史*」的なある種の事実(祖先たちの《上》に起こったあるできごと)が、そのことの重大さと信じ難さのために、われわれによってハンドルし切れないこととして隠されたということなのである。それは、「隠しながら伝える」を本義とする秘教的/神秘主義的伝統とその価値を理解する者たちにとっては、あまりに自明なことであるが、真実を述べ伝え、危機への意識を共有すべき役割を持っていた筈の幾つかの宗教が、その役割上の転向を起こし、隠すだけの組織と堕してしまったことにも原因がある。それはそれだけで論じるに値する課題を持つのであるが、「忘れられた宗教の機能」についての長い補足でも説明したように、宗教がそのような転向**を行ない、真実の「保存と伝達」から、真実の「積極的隠匿」へと走るのは、人間の組織としての宗教団体が、言わば資本主義に象徴されるような近代主義の片棒を担ぐことになってしまうことにも原因を求めることができる。それはこうしたヒトのヒューマニティの目醒めという力強い流れには宗教さえ抗することができなかったこと、そして組織としての生き残りを優先すれば、その発足の理由(悲劇の回避のための知恵の伝承)さえも忘れることができたこと、などが挙げられるであろう。
* 「歴史」と括弧付きで表記したのは、歴史時代(有史以降)が記録が残っている時代という意味であるならば、記録のないきわめて古層の歴史的事実を扱うものであるからである。アカデミックな言い方をすれば有史以前であるからそれは歴史と呼ばれるべきものでないという意見もあろう。
** entee memoで「転向」という言葉を検索した結果
確かにオカルトはスピリチュアルな問題とも接していることは否めない。したがって広義にはスピリチュアルなこととして論じることも可能だが、それは今の段階では問題を不要に複雑にしてしまう時期尚早な態度であるということができよう。問題を精神論にまで発展させる以前に、歴史的事実としての「オカルト的事態」「隠された歴史」があったということを実感として諒解することが、目下のところ最優先されるべきなのである。
例えば、コリン・ウィルソンの名著『The Occult オカルト』が、オカルト領域を真面目に言わば肯定的に論じたこともあり、その言葉の名誉挽回を図ったと言うこともできるばかりか、その著書自身が知的興奮を引き起こすに十分なものであったとも言えるのであるが、彼自身のオカルト理解が、結局その後の彼の関心が向かうところのESP(超能力)や魔術といった方面の「疑似オカルト」に引っ張られていることは否めず、《オカルト》という言葉の(歴史的に隠された秘教的伝統であるという意味での)正統的な理解を助けるものではなかったのは残念としか言いようがないのである。
だが、著書全体がわれわれに向けさせようとしている領域の面白さは否定のしようがないと思えたので、敬意を表してその著書の英語版表紙の画像を添付した。
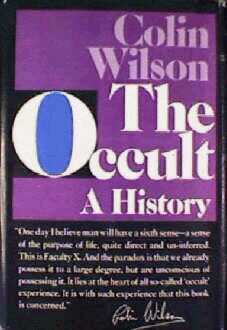
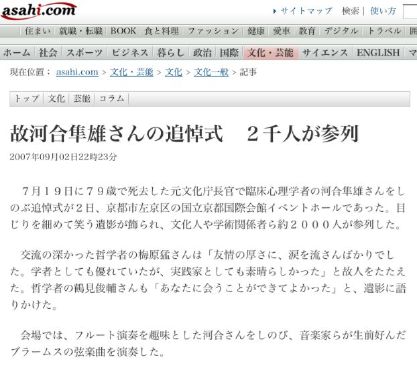


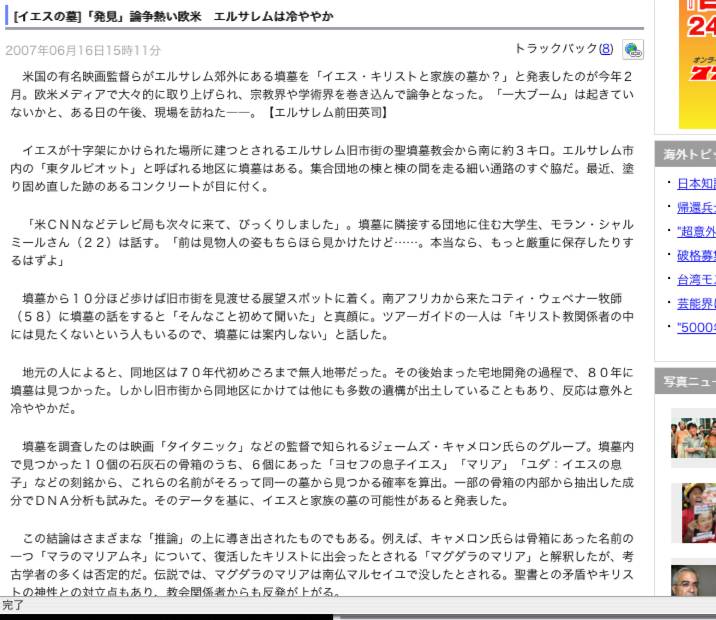 に。
に。